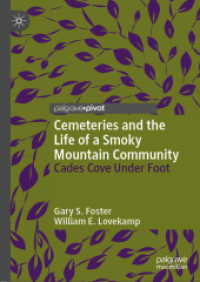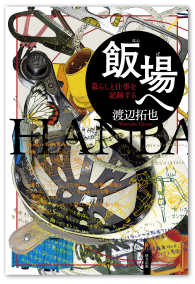出版社内容情報
近世後期から明治前期までの,水運・海運・鉄道・道路の発展,宿財政や飛脚問屋の変貌,地域産業,都市経済圏の形成を中心に,交通・運輸の近代化を草の根に探る。
内容説明
わが国の近代的交通・運輸システムはいかに成立したか。近世後期から明治前期までの、水運・海運・鉄道・道路の技術的発展、宿財政や飛脚問屋の変貌をはじめ、地域の産業と商品流通、産鉄市場、鉄道経営と「巡礼」文化、都市化と経済圏の形成等々にわたり、多角的かつ実証的に分析。
目次
第1編 近世後期の交通と運輸(近世後期における東海道舞坂宿の宿財政;近世甲府飛脚問屋京屋と為登糸;近世中後期の商品流通と地域間紛争―浦賀奉行と江戸町奉行の紛争処理;銚子醤油醸造業と利根水運)
第2編 幕末・明治前期の交通と輸送(幕末における助郷役負担―相州大住郡大磯宿の雇替人馬;幕末・維新期における産鉄市場の展開;明治前期における全国的運輸機構の再編―内航海運から鉄道へ;明治前期における鉄道建設構想の展開―井上勝をめぐって;明治前期の内陸水運と道路輸送―上利根川水系の河岸場を中心として;明治初期の鉄道における客車の発達)
第3編 近代社会成立期の交通と運輸(千住馬車鉄道の設立と経営;町村財政と道路改修;四日市港をめぐる海運の動向;神奈川県川崎における鉄道網の形成;鉄道経営の成立・展開と「巡礼」文化;中京経済圏の形成過程)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
0
e012、東海道の宿場町の経営難航や、鉄の近代前後の歴史、銚子の手船輸送など。交通という共通点はあるものの、その周辺事情という側面が大きかったでしょうか、なんというかこの手の話がどのように交通に影響を及ぼしたのかまでは触れてないので。一つ大きな内容としてあったのが近代を代表する鉄道と、一度それを差し止め、海運中心にする、という宣言があったのだという辺りかな(明治8年、今の東海道線ルートとは別ルートで東西幹線予定)。当時の海運を担ってたのが三菱商船で、その政治影響力もあったそうですが知らんこと一杯あるなぁ。2014/01/12