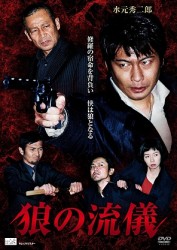目次
第1章 近代社会における近代的なるもの
第2章 ヨーロッパの合理性
第3章 近代社会の固有値としての偶発性
第4章 未来の記述
第5章 非知のエコロジー
著者等紹介
ルーマン,ニクラス[ルーマン,ニクラス][Luhmann,Niklas]
1927年ドイツのリューネブルクに生まれる。1968‐1993年ビーレフェルト大学社会学部教授。70年代初頭にはハーバーマスとの論争により名を高め、80年代以降「オートポイエーシス」概念を軸とし、ドイツ・ロマン派の知的遺産やポスト構造主義なども視野に収めつつ、新たな社会システム理論の構築を試みる。90年前後よりこの理論を用いて現代社会を形成する諸機能システムの分析を試み、その対象は経済、法、政治、宗教、科学、芸術、教育、社会運動、家族などにまで及んだ。1998年没
馬場靖雄[ババヤスオ]
1957年、新潟県生まれ。1988年、京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。現在、大東文化大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
自己言及が無限後退や矛盾に見えるのは、観察者と対象を分離するファーストオーダーの認識論が人間の自己同一性とそれを基点とする合理性重視の意味論に固執するからである。そのような明察への希求に盲目が隣り合う葛藤を生む「近代の観察」が開くのは、観察者は区別する性質を持つが自らを対象と分離できないという行為論的な認識論であり、そこから観察は相互作用するセカンドオーダーへシフトする。本書は、分離と区別の混淆して存在論への郷愁を引き起こす従来の認識論の「何を区別するか」という問いを「どのように区別するか」に置き換える。2024/07/14
Akinobu Otani
0
再読。2015/10/25