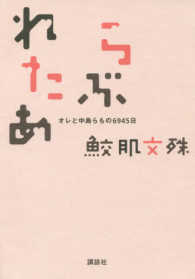目次
“三角形的”欲望
人間はお互いにとって神である
欲望の変貌
主人と奴隷
「赤」と「黒」
スタンダール、セルバンテス、フロベールにおける技法の諸問題
主人公の苦行精神
マゾヒスムとサディスム
プルーストの世界
プルーストとドストイェフスキーにおける技法の諸問題
結び
著者等紹介
ジラール,ルネ[ジラール,ルネ][Girard,Ren´e]
1923年南フランスのアヴィニョンに生まれる。パリの古文書学院、アメリカのインディアナ大学で学業を修め、同大学をはじめジョンズ・ホプキンズ大学、ニューヨーク州立大学などを経て1981年からスタンフォード大学のフランス語学・文学・文明の教授。独自の模倣理論・三角形的欲望理論・暴力理論をもとに、文学・社会学などの分野で注目すべき評論を行なっている
古田幸男[フルタユキオ]
1930年生まれ。東京都立大学大学院仏文学科修士課程修了。法政大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
48
小説論として書かれているため、題材とされている作品内の固有名に沿い議論がちりばめられています。恐らく、そのことが本書を読み難くさせています。人間の欲望は直接みえない。媒体(媒介)によってはじめて主体は対象の意味を知るという、主体、対象、媒体の三角形の関係を論じていることになっていますが、どこまで本書では論じられていて、巷間どこまで認識されているのか、かなり疑問の残る本でした。主体は媒体をみ続けることで、いつの間にか対象ではなく媒体の虜になる。依存症や媒体=エクリチュールといった議論への展開が考えられます。2022/03/02
鏡裕之
6
サブタイトルは「ロマンティークの虚偽とロマネスクの真実」。実はこれが原書のタイトル。欲望の現象学は日本版でつけられたもので、あまり中身を表していない。現象学っぽいところはゼロ。欲望に対する理論がメインではない。セルバンテス、スタンダール、フローベール、プルースト、ドストエフスキーの小説でどのように欲望が描かれてきたのかを著したものである。上記作家の作品で欲望がどんなふうに扱われ、どんな特徴を持っているか、それを記している。欲望についての理論書ではない。文学の本。「タイトルの虚偽」と副題をつけたい。2021/06/20
左手爆弾
3
欲望とは主体・媒体・対象の3つがあってはじめて成立するものであり、決して主体の中に自発的に生じるものでもなく、対象が主体を触発するだけでも生じない。つまり、欲望は無からの創造ではない。他人が常におり、それに対して想像力の作用が働き、それ故に欲望がはじまる。対象の持つ聖性や形而上性は、「距離」に依存する。欲望は常にそうした距離、とりわけ接触において伝染する。文芸評論から極めて一般的な欲望の理論を仕上げたという点で優れている。ただし、一般的すぎるが故に、その適用については慎重になるべきであろう。2016/02/25
ぬまけん
1
Z2024/06/09
Eleanor
0
プルースト読んでてよかった!の読書2025/09/19