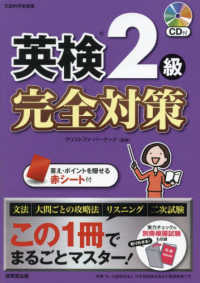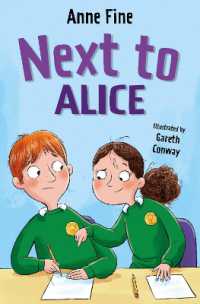出版社内容情報
アルファベット文字の起源を紀元前1700年頃にまで遡り,近代文字として案出され発達する道のりを豊富な図版を例示して明らかにする。西洋文明の源流への誘い。
内容説明
文字を書くことは話し言葉を体系的に記述するために図記号を使用することであり、初期の文字は語あるいは音節を表わす数多くの絵文字から成り立っていた。この文字記号の数を最低限に減らすこと、それがつまりアルファベットの案出であった。ギリシア・ローマ時代に導入され西洋文明の展開に重要な役割を果たしてきたアルファベット文字の発達の歴史を、紀元前1700年頃のその発端にまで遡り、近代文字として具体化するまでの道のりをたどるもので、西セム語の碑銘学・古文書学への入門書として、読者を古代のロマンに誘う。
目次
1 序章(碑文と写本;碑銘学と古文書学;文字と書体の発展;セム諸語と諸文字)
2 セム文字の出現(背景;アルファベットの始まり)
3 南セム文字
4 西セム文字(フェニキア文字;ヘブル文字;アラム文字;フェニキア文字、ヘブル文字、アラム文字の形状の比較;イスラエルの近隣の諸文字;ヘブル文字からユダヤ文字への変化)
5 アラム文字から生まれ出た諸文字(イラン圏におけるアラム文字;東方におけるアラム文字;ナバテア文字と、アラビア文字の誕生;ユダヤ文字)
6 ギリシア文字アルファベットの古さ
著者等紹介
ナヴェー,ヨセフ[ナヴェー,ヨセフ][Naveh,Joseph]
1928年生まれ。北西セム語古文書学、文字論の世界的権威で、1977年に退官するまでイスラエルのヘブル大学の西セム語碑文学教授を務めた。1955年から71年までイスラエル考古学庁に属し、エン・ゲディをはじめ多くの発掘調査に関わった。1971年以降は主に碑文学の研究に従事し、アラム語、フェニキア語、古ヘブル語の諸碑文の解読とそれらの比較研究を行なっている
津村俊夫[ツムラトシオ]
1944年生まれ。一橋大学商学部卒業。米国アズベリー神学大学、ブランダイス大学大学院博士課程修了(Ph.D.取得)。ウガリト学、セム語学専攻。ハーバード大学特別研究員、英国ティンデル研究所研究員(Fellow)、筑波大学文芸言語学系助教授を経て、現在、聖書神学舎教師会議長、旧約学教師
竹内茂夫[タケウチシゲオ]
1961年生まれ。京都産業大学外国語学部言語学科卒業。同大学院修士課程外国語学研究科修了、筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得退学(文学修士)、文部省学術振興会特別研究員(PD)、ライデン大学文学部客員研究員などを経て、京都産業大学文化学部准教授。古典ヘブライ語を中心にしたセム語学、一般言語学専攻
稲垣緋紗子[イナガキヒサコ]
1945年生まれ。国際基督教大学教養学部語学科卒業。ジャパン・ミッショナリー・ランゲージ・インスティテュート(JMLI)講師。ECC外語学院講師。聖書宣教会聖書神学舎卒業後、パリ・プロテスタント日本語キリスト教会伝道師を経て、現在、日本福音キリスト教会連合岩井キリスト教会副牧師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。