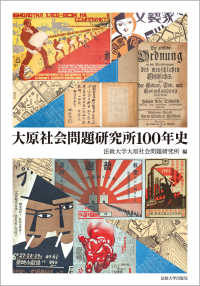内容説明
歴史を素材にしたルーマンの知識社会学再考。
目次
第1章 社会構造とゼマンティクの伝統
第2章 上流諸階層における相互行為―十七世紀と十八世紀におけるそのゼマンティクの転換について
第3章 初期近代の人間学―社会の進化問題の理論技術上の解決
第4章 複雑性の時間化―近代の時間概念のゼマンティクについて
第5章 自己言及と二項図式化
著者等紹介
ルーマン,ニクラス[ルーマン,ニクラス][Luhmann,Niklas]
1927年ドイツのリューネブルクに生まれる。1968‐1993年ビーレフェルト大学社会学部教授。70年代初頭にはハーバーマスとの論争により名を高め、80年代以降「オートポイエーシス」概念を軸とし、ドイツ・ロマン派の知的遺産やポスト構造主義なども視野に収めつつ新たな社会システム理論の構築を試みる。90年前後よりこの理論を用いて現代社会を形成する諸機能システムの分析を試み、その対象は経済、法、政治、宗教、科学、芸術、教育、社会運動、家族などにまで及んだ
徳安彰[トクヤスアキラ]
1956年佐賀県に生まれる。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。法政大学社会学部教授。社会システム論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たばかるB
13
本書におけるルーマンの社会変動をまとめた論文“https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr1950/49/4/49_4_620/_pdf” 機能分化、ゼマンティクの変化、複合性の増大がキーターム。社会構造の変化が何らかの形で起こったとき、以前まで通じていた「意味」では把握できず、複合性が増大する。だからより複合性を縮減するような「意味」が例えば過去の知識集合体から選択されるなどして、整備される。最初の構造変化を第一次変化、次を第二次変化という。2022/10/28
roughfractus02
7
中世の階層化社会から近代の分化社会の変容を全体社会から見た場合、分出する各閉鎖系システムを注視する著者は、このような分化社会のコミュニケーションが複合性の増大をもたらし、偶発事に対処する過剰な構えを作り出さなければならなくなったという。一方、この歴史的変容をもたらした啓蒙が開かれた運動である点をドイツ歴史学は前景に押し出しながら複合性を増大させる危機として反省することはなおざりにしてきたと批判する。本書は、分化社会が危機への対処として意味処理規則のストック=ゼマンティクを形成してきた点から検討を始める。2024/08/03
抹茶ケーキ
0
近代以降社会は機能分化(=複雑化)している。そのような複雑性に対応するためには何らかの形でその複雑性を縮減しなくてはならない。そのような方策の一つがゼマンティクの変容である。そのような意味でゼマンティクは、社会構造と連関している。大筋はこんな感じだと思うけど、細部がほとんどわからなかった。2016/02/27
-

- 電子書籍
- 弐の国の引継書【分冊版】 18 MFC
-

- 電子書籍
- 最下層の僕が奴隷を飼ったら ―監禁観察…