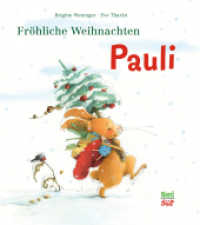出版社内容情報
あらゆる人間的言説におけるジャンルの考察を通じて,文学作品を成立させる制度としてのジャンルのメカニズムを探求する。『象徴の理論』以来の実践的言語活動論。
内容説明
言葉遊びからドストエフスキーまで、あらゆる人間的言説におけるジャンルの考察を通して、文学作品を成立させる制度としてのジャンルのメカニズムを探求する。『象徴の理論』『象徴表現と解釈』の言語象徴理論をより実践的に展開する。
目次
文学の概念
レッシングによるポイエティックとポエティック
諸ジャンルの起源
物語の二つの原則
精神病者の言説
構成としての読書
詩をめぐって
他者性のたわむれ―『地下室の手記』
エドガー・ポーの境界
虚無の認識―『闇の奥』
『厄介な年ごろ』
『イリュミナシオン』
なぞなぞ
呪術の言説
機知
言葉遊び
著者等紹介
トドロフ,ツヴェタン[トドロフ,ツヴェタン][Todorov,Tzvetan]
1939年、ブルガリアに生まれる。ロラン・バルトの指導のもとに『小説の記号学』(67)を著して構造主義的文学批評の先駆をなした。『象徴の理論』(77)、『象徴表現と解釈』(78)、『言説の諸ジャンル』(78)、『批評の批評』(84)で文学の記号学的研究をすすめるかたわら、『他者の記号学―アメリカ大陸の征服』(82)以後、記号学的見地から「他者」の問題に関心を深め、『ミハイル・バフチン―対話の原理』(81)、『アステカ帝国滅亡記―インディオによる物語』(83)などを刊行している。91年、『歴史のモラル』でルソー賞を受賞。現在、国立科学研究所(CNRS)の芸術・言語研究センターで指導的立場にある
小林文生[コバヤシフミオ]
1950年生。東北大学文学部卒。東北大学大学院博士後期課程中退。20世紀仏文学専攻。東北大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 刑事政策 (第2版)