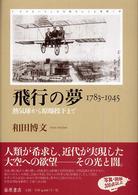内容説明
茶は、どのように広まり、どのように親しまれたのか?鎌倉期に行われた闘茶や、室町期の会所や草庵での楽しみ、信長や秀吉が愛した茶道具、利休が大成した「わび茶」…。中国伝来の茶は、時代ごとに様々なかたちで親しまれてきた。公家、武士、僧侶、そして庶民、それぞれの身分の人々はどのように茶を楽しんだのか?茶の作法はどのようにして生まれたのか?日本人の心に寄り添う、茶の湯の歴史を楽しく解説!図版多数掲載!
目次
一 茶の文化
二 茶の湯
三 茶の湯の到達点
四 茶の湯の楽しみ
五 茶の湯の世界の広がり
六 近代の茶の湯
著者等紹介
五味文彦[ゴミフミヒコ]
東京大学・放送大学名誉教授、足利学校庠主。専門は日本史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ここぽぽ
16
昔からのお茶にも、深い歴史があり奥深い。武士の談話の場所から、女性の花嫁修業の所作になっていく茶の湯。贅を尽くしたモノから進化し、日常的に庶民にも嗜まれていく。現代に生きて茶を飲める贅沢が幸せと感じた。2025/05/02
於千代
2
茶の伝来から、戦後の家元制度の成立までをたどる一冊。 歴史を通して俯瞰してみると、茶の楽しみ方には決して決まった「かたち」があったわけではなく、時代ごとに変遷し、多様な姿を見せてきたのだと実感させられる。 印象的だったのは、古田織部のエピソード。彼は「十文字」という茶器を使っていたが、割ったうえで削って小さくして継ぎ直して使っていたという。ほかにも、掛け物を「格好悪い」という理由で切り取るなど、奇矯ともいえる行動の数々が紹介されており、「この人、世の宝を損なふ人なり」と評されたのも納得してしまった。2025/06/18
Go Extreme
1
「茶寄合・闘茶といった娯楽的・社交的行為の中で、茶が文化実践へと昇華していく」 「わび茶」の精神性の深化と構造化」 「道具・茶室・作法にこめられた美学と宗教性」 「千利休による簡素と精神性の極致としての茶の湯の完成」 「非日常的な精神世界を創出する場としての茶の湯が体系化される」 「茶の湯」がもたらすのは単なる味覚的喜びでなく、身体性・空間・時間を含んだ総合的な快楽と精神交流」 「家元制度による伝承と秩序化」 「茶の湯が「閉じた文化」から「ひらかれた文化」へと拡張」 「わび・さび・幽玄:精神性と簡素の美」2025/04/02


![The Last King of Ulster [By E. Getty]](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)