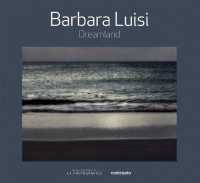出版社内容情報
天皇をめぐる文化体系は、いかに復古・継承されたのか―政治的・社会的状況が混迷しつつあった江戸時代後期、神事・朝儀の再興と復古に尽力し、歴代最後の「生前退位」を行った光格天皇。
近代天皇制の礎を築いたとされるその営みの淵源・背景にある文化体系・歴史的状況はいかなるものであったのか。
天皇を中心に形成された歌壇とそこで培われた人的ネットワーク、そして、文化の継承・展開を支えた学芸と出版を歴史的に把捉することで、光格天皇、その兄である妙法院宮真仁法親王の文化的営みの意義を明らかにする。
*光格天皇(こうかくてんのう)とは…
第119代天皇。在位、安永八(1780)年11月25日?文化十四(1817)年3月22日。
今上天皇直系の閑院宮家から出た初代の天皇。生前退位をした歴代最後の天皇としても知られる。
好学としても名高く、朝廷の復権を願い、神事・朝議の復古・再興に力を入れ、近代天皇制の礎を築いた。
序言 盛田帝子
緒論
光格天皇をどうとらえるか 藤田覚
第一部 近世歌壇における天皇公家
後水尾院と趣向 大谷俊太
霊元院の古今和歌集講釈とその聞書―正徳四年の相伝を中心に 海野圭介
冷泉為村と桜町院 久保田啓一
孝明天皇と古今伝受―附・幕末古今伝受関係年表 青山英正
武者小路実陰家集の二系統について―堂上〈内部〉の集と〈外部〉の集 浅田徹
香川黄中の位置 神作研一
第二部 朝廷をめぐる学芸・出版
『二十一代集』の開板―書肆吉田四郎右衛門による歌書刊行事業の背景 加藤弓枝
『大日本史』論賛における歴史の展開と天皇 勢田道生
中村蘭林と和歌―学問吟味の提言と平安朝の讃仰 山本嘉孝
江戸時代手習所における七夕祭の広がりと書物文化 鍛治宏介
書道大師流と近世朝廷 一戸 渉
梅辻春樵―妙法院宮に仕えた漢詩人 合山林太郎
第三部 光格天皇・妙法院宮の文芸交流
寛政期新造内裏における南殿の桜―光格天皇と皇后欣子内親王 盛田帝子
実録「中山大納言物」の諸特徴―諸本系統・人物造型を中心に 菊池庸介
冷泉家における光格天皇拝領品 岸本香織
妙法院宮真仁法親王の文芸交流―『妙法院日次記』を手がかりとして、和歌を中心に 飯倉洋一
小沢蘆庵と妙法院宮真仁法親王 鈴木淳
千蔭と妙法院宮 山本和明
あとがき 飯倉洋一
執筆者一覧
飯倉洋一[イイクラヨウイチ]
編集
盛田帝子[モリタテイコ]
編集
内容説明
政治的・社会的状況が混迷しつつあった江戸時代後期、神事・朝儀の再興と復古に尽力し、歴代最後の「生前退位」を行った光格天皇。近代天皇制の礎を築いたとされるその営みの淵源・背景にある文化体系・歴史的状況はいかなるものであったのか。天皇を中心に形成された歌壇とそこで培われた人的ネットワーク、そして、文化の継承・展開を支えた学芸と出版を歴史的に把捉することで、光格天皇、その兄である妙法院宮真仁法親王の文化的営みの意義を明らかにする。
目次
緒論 光格天皇をどうとらえるか
第1部 近世歌壇における天皇公家(後水尾院と趣向;霊元院の古今和歌集講釈とその聞書―正徳四年の相伝を中心に;冷泉為村と桜町院 ほか)
第2部 朝廷をめぐる学芸・出版(『二十一代集』の開板―書肆吉田四郎右衛門による歌書刊行事業の背景;『大日本史』論賛における歴史の展開と天皇;中村蘭林と和歌―学問吟味の提言と平安朝の讃仰 ほか)
第3部 光格天皇・妙法院宮の文芸交流(寛政期新造内裏における南殿の桜―光格天皇と皇后欣子内親王;実録「中山大納言物」の諸特徴―諸本系統・人物造型を中心に;妙法院宮真仁法親王の文芸交流―『妙法院日次記』を手がかりとして、和歌を中心に ほか)
著者等紹介
飯倉洋一[イイクラヨウイチ]
1956年生まれ。大阪大学教授。専門は日本近世文学
盛田帝子[モリタテイコ]
1968年生まれ。大手前大学准教授。専門は日本近世文学、和歌文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- DVD
- 子連れ狼 第十二巻(2)