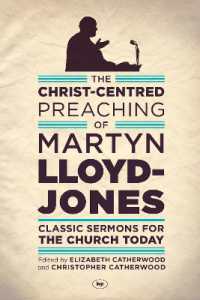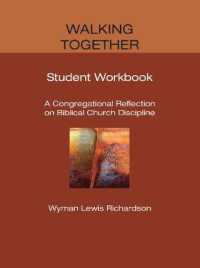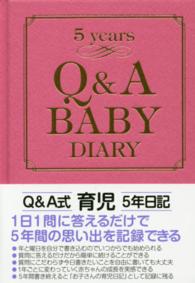内容説明
関東における政治・宗教・学問の展開、禅林におけるヒト・モノ・思想の流入と伝播、堂上・地下における多様な文化の結節点としてある連歌―多元的な場を内包しつつ展開した室町期の文芸テキストを、言語・宗教・学問・芸能など諸ジャンルの交叉する複合体として捉え、その表現の基盤と成立する場を照射することで、室町の知的環境と文化体系を炙り出す。
目次
第1部 中世関東の時空(中世和歌の一環境;庭訓往来を巡る註釈の学―真名抄周辺資料点綴;述馬迦異聞;雑談と問答―『旅宿問答』私註)
第2部 唱導と学文と(中世陰陽道の片影―『塵滴問答』略註;「名語記」断章;歌、遊び、秘伝;中世注釈史のために)
第3部 禅林の影(紅葉のふみ―年中行事歌合の一首から;「題葉譚」逍遥;太平記受容史一斑―『太平記賢愚抄』をめぐって;「唐梅」抄)
第4部 堂上連歌、地下連歌(『夫木和歌抄』の享受と連歌;室町前期の北野信仰と伏見宮;「発句大まはし」のこと;連歌と説話の場)
著者等紹介
鈴木元[スズキハジメ]
昭和38年愛知県生まれ。昭和60年愛知県立大学文学部卒業。平成9年中京大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。現在、熊本県立大学文学部教授。専門は、日本中世文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。