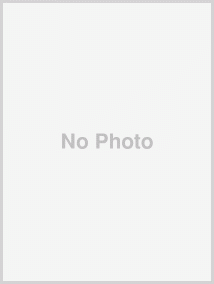内容説明
日本の近代化とのかかわり、西洋文化からの衝撃、芸術における形式の破壊と創造など幅広い問題を含む『舞姫』。本書では、鴎外の執筆行為そのものに先駆性を見出し、その特色を探るとともに、西欧文化との接触が主題や文体の選択にどのような手掛かりを与えたのかを考察する。さらに、執筆の動機、事実と創作の境界、文学史的位置付け、現代語訳の意義など、多角的な読みのための方法論・新視点を紹介する。
目次
第1章 『舞姫』の形成―人物造型を中心に(『舞姫』はなぜ書かれたか?;「エクソフォニー小説」としての『舞姫』―実体験の「翻訳」という創作 ほか)
第2章 『舞姫』の表現―その内的しくみ(鴎外『舞姫』論―記憶を語る語り・「想」の表象;『舞姫』における心的なるもの ほか)
第3章 『舞姫』の問題点と新視点―留学体験との関係(『舞姫』の悲劇;文学の自立―鴎外の活路 ほか)
第4章 『舞姫』の位相―『舞姫』以前・以後の文学(『舞姫』の位相―表現・文体・文学的系譜の視点から;『舞姫』の恐るべき先駆性―近代文学研究状況批判/「語り手」の語らない自己表出 ほか)
著者等紹介
清田文武[セイタフミタケ]
1939年生まれ。新潟大学名誉教授。中国・東北師範大学客座教授。日本近代文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
スイ
5
作品についての論文集を読むと、いつも思う。 人はどんな作品からでも、自分が読みたいものを読み取るんだなと…。 面白かったけども。2017/10/28
Taka
1
舞姫・雁。 学生時代に、森鴎外の文体は美しく参考にすべきといわれた。好き嫌いが分かれるところだが、今読み返してみても、いかにも男性的文体であり、自分が三島由紀夫の文体が好きなことにも通じるところがあるのかと感じた。男性的な文体の本を読んだ後には女性的な文体の本を欲する自分がいる。2014/09/16
Yuki
0
井上優氏のものの中盤あたりまでが白眉。 他氏の論考で力みがあるものが少ないのが残念。 あなたにとっての舞姫の思い出なんて語ってんなよと思ってしまうようなものもあり。お値段相当かというとそうではないでしょうね。2017/12/26