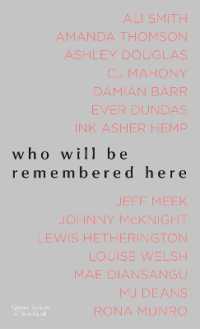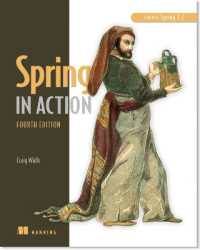出版社内容情報
720 年(養老4)に正史として撰進された『日本書紀』は、天皇・文人貴族らによる講書、そしてその読み方を書き入れた写本などの形で伝えられ、古辞書・注釈書類にもその成果が取り込まれるなど、これらの学問の痕跡は古代の和訓・アクセントを今に伝える貴重な資料群である。
『日本書紀』古写本および関連資料に残された和訓・声点を網羅的に調査・検討、さらにそれらが付され伝えられていったその過程を明らかにすることにより、古代日本語の学問体系やアクセント史における新知見を提示する。
内容説明
『日本書紀』古写本が伝えてきたものは何か―720年(養老4)に正史として撰進された『日本書紀』は、天皇・文人貴族らによる講書、そしてその読み方を書き入れた写本などの形で伝えられ、古辞書・注釈書類にもその成果が取り込まれるなど、これらの学問の痕跡は古代の和訓・アクセントを今に伝える貴重な資料群である。『日本書紀』古写本および関連資料に残された和訓・声点を網羅的に調査・検討、さらにそれらが付され伝えられていったその過程を明らかにすることにより、古代日本語の学問体系やアクセント史における新知見を提示する。
目次
第1部 『日本書紀』声点本の資料価値に関する研究(『日本書紀』神代巻の声点;乾元本紀所引『日本紀私記』の声点について;乾元本『日本書紀』万葉仮名訓の声点;岩崎本『日本書紀』の声点;訓読漢字の声点のアクセント表示法;『日本書紀』被訓注字の声点;『古語拾遺』の声点;『日本書紀』声点本の濁音表示;『古語拾遺』声点本の濁音表示;『日本書紀α群の万葉仮名』―原音声調と日本語アクセントの対応)
第2部 『日本書紀』声点本の成立過程に関する研究(『弘仁私記』序の「以丹点明軽重」;乾元本紀所引『日本紀私記』の万葉仮名;『日本書紀』古写本中の万葉仮名表記の和訓;『和名抄』所引『公望私記』の万葉仮名訓;延喜『公望私記』の構造;日本紀講書とアクセント)
第3部 平安時代京都アクセントに関する研究(和語声点資料の差声方式;助詞「の」のアクセント;アクセント史研究における拍内下降;平声軽点の消滅過程;アクセント体系大変化の要因;『金光明最勝王音義』所載「以呂波」のアクセント;いろは歌の作者について―いろは48字説の検討)
著者等紹介
鈴木豊[スズキユタカ]
1958年生まれ。文京学院大学外国語学部教授。専門は日本語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
中村明裕