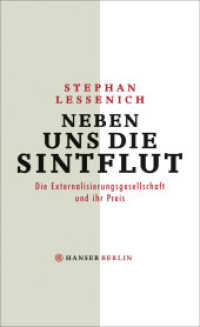内容説明
天麩羅・鮨・おでんにかまぼこ・蕎麦・ちくわから餃子にハヤシライスまで―身近な食べ物の語源を辞書・随筆ほか諸文献から博捜。日本人の知恵と感性を味わう。
目次
1 店屋物(テンプラ;すし;弁当;焼き物;鍋物;おでん;麺類;中華料理)
2 家庭の味(惣菜;漬物;汁物;めし)
3 菓子(餡菓子;餅菓子;干菓子;南蛮菓子)
著者等紹介
小林祥次郎[コバヤシショウジロウ]
昭和13年2月栃木県栃木市に生まれる。昭和35年3月東京教育大学文学部文学科卒業。平成13年3月小山工業高等専門学校教授を退官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みずさわゆうが
4
網羅した研究書というより、著者の気になる「くいもの」を探求していく書。あまり要領を得ない書きぶりであるが、考証しつつ、著者の体験や意見を挟むのが面白い。『日葡辞書』を引っ張り出そうか、国会図書館などで『和漢三才図会』や『七十五日』あるかなあ、と思わせた。また、有名人にこじつける語源説はたいてい違う、というのは面白い発見。文化というものはそういうものである。そもそもあるへい糖・松風・いとこ煮・船場汁・あちゃら漬など、そもそも紹介された「くいもの」自体が耳慣れないものもあり、楽しく調べることができた。2023/05/27
姐御
3
語源、と言うよりはこの食べ物はこういう作品に登場していた、こういう文献にはこのように書かれていた、と言うその食べ物に対する説明が多かった気がします。 食べ物の表現方法を探していたので、個人的には文章が固いのが難点でした。2016/04/26
gibbelin
2
くいもんのハナシには罪がない、と云いますが。 たぬき、きつねは京阪神人として自分も語れそうな気もするけれど、おかめ・しっぽく、あたりは、わからんですね。飛竜頭、ゆかり、せんば煮、なま節、のっぺい汁、鯉こく、あちゃら漬け…あたりは、わが走馬灯セトリの食編に並べたい。2023/03/21
takao
2
ふむ2022/07/17
マギー
2
日本の食べ物の語源について書かれた本。 昔の書物の引用がメインなので、信憑性があるのは良いことかもしれない。その反面、諸説ありすぎて印象に残りづらい。 そもそも見聞きしたことない地方の食べ物の語源の話もあり、ためになった。2019/06/04
-
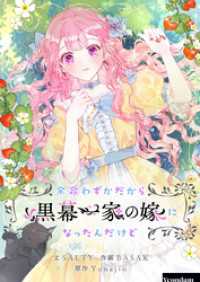
- 電子書籍
- 余命わずかだから黒幕一家の嫁になったん…