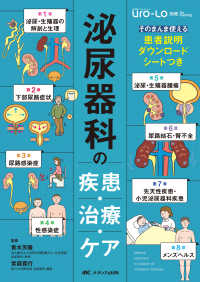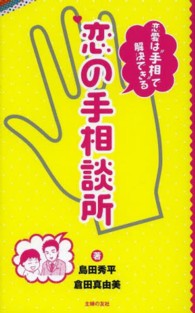- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
宗教的な講や田の水引きの農作業など村人が集まる機会に、独特の節回しで本を読んで聞かせる人びと、ホンヨミ。彼らによって読み伝えられた物語や由緒は、語り継がれ、また、時には書き写されながら、地域社会の共通の知となっていった。
地域社会において、〈本〉は、そして〈読む〉ことと〈書く〉ことはどのような意味を持っていたのか。三陸地方を中心に、ホンヨミに触れてきた人びとへの直接の取材から浮かび上がる民俗社会を描き出す。
内容説明
“本”と呼ばれるモノはいかに民俗社会と関わってきたのか―。宗教的な講や田の水引きの農作業など村人が集まる機会に、独特の節回しで本を読んで聞かせる人びと、ホンヨミ。彼らによって読み伝えられた物語や由緒は、語り継がれ、また、時には書き写されながら、地域社会の共通の知となっていった。地域社会において、“本”は、そして“読む”ことと“書く”ことはどのような意味を持っていたのか。三陸地方を中心に、ホンヨミに触れてきた人びとへの直接の取材から浮かび上がる民俗社会を描き出す。
目次
第1部 「本読み」の民俗(「本読み」の民俗―宮城県気仙沼地方の事例から;文字を聞く・文字を語る―「本読み」の民俗誌)
第2部 書物と語り(語り伝えと書き伝え―「歌津敵討ち」をめぐって;「女川口説」の伝承誌;ムラの歴史を語ること―仙台藩入谷村の「郷土誌」の発生;「入谷安部物語」の伝承世界)
第3部 漁村社会と文字文化―呪いから漁業権まで(「歌詠み」の民俗―宮城県気仙沼地方の事例から;花渕善兵衛のお通りだ―蛇除けの呪いを伝える家の伝承;鮭漁をめぐる伝説と歴史伝承―気仙川の漁業権の解放と規制;「浮鯛抄」をめぐる文字と口頭の伝承)
著者等紹介
川島秀一[カワシマシュウイチ]
1952年生まれ。東北大学災害科学国際研究所シニア研究員。専門は民俗学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イトノコ
bapaksejahtera
takao
johnlenon64
ガジ