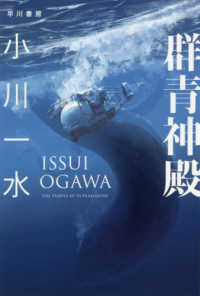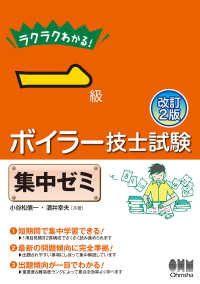出版社内容情報
政治とナショナリズムに現れる権力に迫り痛みの痕跡から歴史を捉え直す〈従軍慰安婦問題〉が1990年頃に日韓の政治的な問題として表面化した一方で、日本人「慰安婦」は「加害国の被害者」という立場ゆえこれまで可視化されていなかった。
雑誌や新聞記事などのメディア表象や運動資料を分析し、「慰安婦」を語る言説が、「被害者」「加害者」像を形成し、忘却を伴いつつも、「慰安婦」問題をいかに構築していったのか、その過程を明らかにする。
さらに、城田すず子ら当事者たちの残した手記を手がかりに、暴力的な出来事を経て、彼女らがどのような戦後を生きてきたのかを浮かび上がらせる。
はじめに
序章 「慰安婦」問題へのアプローチ
1.「慰安婦」問題再考―日本人「慰安婦」に注目して
2.日本人「慰安婦」をめぐる議論
3.「慰安婦」制度をめぐる先行研究
4.本書の構成
第1部 〈従軍慰安婦問題〉の構築
第1章 戦後の「慰安婦」言説―社会問題化以前
1.「慰安婦」の記憶と〈強制連行〉の問題化
2.国会で語られた「慰安婦」
3.ルポルタージュの登場
第2章 言説空間の拡大―社会問題化の諸相
1.韓国フェミニズム運動による告発と社会問題化
2.新聞・雑誌にみる〈従軍慰安婦問題〉
3.政治・外交問題としての〈従軍慰安婦問題〉
4.言説空間の振り返り
第2部 社会運動の「慰安婦」言説
第3章 一九七〇―八〇年代フェミニズム運動の「慰安婦」言説
1.〈加害者〉日本人の主体化
2.ウーマン・リブ運動の「慰安婦」テクスト
3.侵略=差別と闘うアジア婦人会議の「慰安婦」テクスト
4.サバイバー被害者=生存者への想像力
第4章 「慰安婦」問題解決運動の言説空間―一九九〇年代初頭を中心に
1.運動の言説空間と日本人「慰安婦」
2.運動関係者が経験した〈従軍慰安婦問題〉
第3部 日本人「慰安婦」の被害をとらえる
第5章 日本人「慰安婦」被害者の語り
1.日本人「慰安婦」被害者の語り
2.城田すず子のテクスト
第6章 日本人「慰安婦」の被害者性
1.被害を不可視化するメカニズム
2.ナショナリズムと性を再び問う
補 論
参考文献
あとがき
木下直子[キノシタ ナオコ]
日本学術振興会特別研究員PD(大阪大学)。特定非営利活動法人社会理論・動態研究所研究員。九州大学大学院比較社会文化学府単位修得退学(2012年)、博士(2013年)。
主な論文に、「聴きとられなかった言葉をめぐって―日本人「慰安婦」に関するフェミニズムの議論の批判的検討」(『理論と動態』社会理論・動態研究所、第7号、2014年)、「フェミニズム運動にとっての日本人「慰安婦」―1970年代ウーマン・リブのテクストを中心に」(チョングンシク・直野章子編『記憶と表象から読む東アジアの20世紀』花書院、2014年)などがある。
内容説明
政治とナショナリズムに現れる権力に迫り痛みの痕跡から歴史を捉え直す―。90年代前後に“従軍慰安婦問題”が日韓の政治的な問題として表面化する一方、日本人「慰安婦」は「加害国の被害者」という立場ゆえこれまで可視化されていなかった。雑誌や新聞記事などのメディア表象や運動資料、城田すず子ら当事者たちの残した手記を手がかりに、「慰安婦」を語る言説が「被害者」「加害者」像を形成していった過程と、当事者たちがどのように戦後を生きたのかを浮かび上がらせる。
目次
「慰安婦」問題へのアプローチ
第1部 “従軍慰安婦問題”の構築(戦後の「慰安婦」言説―社会問題化以前;言説空間の拡大―社会問題化の諸相)
第2部 社会運動の「慰安婦」言説(一九七〇‐八〇年代フェミニズム運動の「慰安婦」言説;「慰安婦」問題解決運動の言説空間―一九九〇年代初頭を中心に)
第3部 日本人「慰安婦」の被害をとらえる(日本人「慰安婦」被害者の語り;日本人「慰安婦」の被害者性)
補論
著者等紹介
木下直子[キノシタナオコ]
日本学術振興会特別研究員PD(大阪大学)。特定非営利活動法人社会理論・動態研究所研究員。九州大学大学院比較社会文化学府単位修得退学(2012年)、博士(2013年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イカ
ami
-

- 電子書籍
- 婚約破棄のその先に ~捨てられ令嬢、王…