内容説明
世界に誇る和食。食材の広がりや食事の作法まで、歴史的検証を重ねながら、長く深い伝統を持つ日本人の食の知恵を紹介する。読めば腹鳴る、日本食卓事情。
目次
第1部 和食の博物誌(米作りとご飯の歴史;日本料理はどのように発達してきたのか;日本酒の文化誌;和の調味料文化)
第2部 日本食の近現代誌(大江戸の食卓事情;変わり行く和の食材;家庭料理の誕生;明日の食生活をどうすればよいか)
著者等紹介
橋本直樹[ハシモトナオキ]
京都大学農学部卒、農学博士、技術士。キリンビール(株)開発科学研究室長、ビール工場長を歴任し、常務取締役で退任。(株)紀文食品顧問、京都大学・東京農業大学非常勤講師を経て、帝京平成大学教授(食文化・栄養学。2010年まで)。食の社会学研究会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
35
稲は日本列島に自生せず、中国大陸から伝えられた作物(016頁)。奈良時代、稲作が律令国家の税収を賄う唯一の重要産業だった(023頁)。3度のご飯を食べるのは江戸時代から(028頁~)。著者は今こそ、ご飯を食べる和食を見直すこと提起する(040頁)。醤(ひしお)とは米、麦、大豆を塩漬けにして発酵させたどろりとした液体。箸は遣隋使が持ち帰ったもの(045頁)。匙を使う習慣は平安時代終わりからなくなった(047頁)。 2016/03/24
Humbaba
8
日本人の主食は米であり、かつては非常に大量の米が消費されていた。しかし、現代においてはその消費量は急激に少なくなっている。社会が豊かになり選択の自由度がましたと考えればそれは幸福なこととも考えられるが、無駄になっている食材の量を考えるとこのままで良いとはいえない。2016/05/15
読書実践家
7
優れた名著。何度でも読みたい。日本の豊かな食生活。多品目で豊富な種類の料理。歴史がある。そして、国内で食料を自給できなくなった。健康食品や添加食品。飽食と欠食が共存する社会。家庭の団欒としての食卓は大事だと思った。2016/02/17
読書実践家
7
楽しく読める。日本の多様な食文化。幅広く、色んな食べ物・料理をアレンジして食卓を彩る。米の消費量が減り続けている。日本の食べ物は美味しい。塩おにぎりでさえ、おいしさを感じる。しかし、人任せな食事や食品不安も高まっているのも事実。日本の食卓はどこへ行くのだろうか。2016/01/31
key
1
縄文時代から現在までの日本食の成り立ちが書かれているので非常に興味深い内容でした。社会の変化に伴い昔のような一家団欒で過ごした食卓が崩壊を向かえている現代は、家族の在り方まで変化をしてしまう危険性があるとのことだそうだ。2016/02/12
-

- 電子書籍
- あざといちゃんとヤンキーくん【タテヨミ…
-
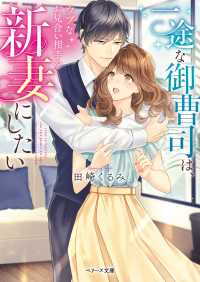
- 電子書籍
- 一途な御曹司は、ウブなお見合い相手を新…
-

- 電子書籍
- 法学教室2016年2月号 法学教室
-

- 電子書籍
- 花の任侠物語しずか(完結版) 2巻 ま…
-
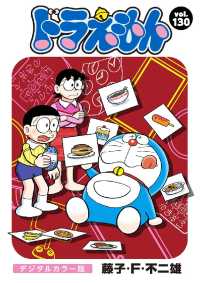
- 電子書籍
- ドラえもん デジタルカラー版(130)




