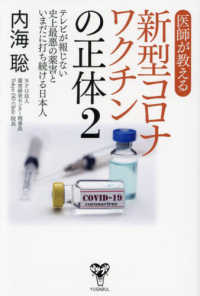内容説明
共産党支配のなかに、「民意」のありかをみきわめる。急成長を続ける中国のネット社会。そこで生まれているさまざまな新語には中国民衆の本心が表されている。権力の目をかいくぐり、たくましく自己主張を始めた網民たち。ここ数年、中国に出現したネット流行語の意味と背景を探ることで、隣国の内情を知り、今後の中国社会がどう変わるのかを考察する。
目次
序章 ネットは中国を変えるか?(「あなたたちは騙されている!」;ネット企業幹部が狂喜した「馬」とは ほか)
第1章 中国の言論空間とインターネット(五億人に達した中国ネット社会;ネット世論の誕生 ほか)
第2章 中国社会を知るためのネットキーワード(発言する網民;網民のユーモア ほか)
第3章 ネットで中国はどう変わる?―安替へのインタビュー(人民日報は主流メディアではない;漁船事件、何が問題だったのか ほか)
著者等紹介
古畑康雄[フルハタヤスオ]
1966年東京生まれ。共同通信社国際局デスク(中国語ニュース担当)。89年、東京大学文学部(中国語中国文学)卒、同年共同通信社に入り、地方支社局を経て97年から1年間、北京の対外経済貿易大学に留学。帰国後、2001年に共同通信の中国語ニュースサイト「共同網」を立ち上げ、現在も編集を担当。同時に中国のメディア、インターネットの研究、執筆にも取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nori_y
3
2012年の本なので、既に中国を取り巻くインターネット環境はガラリと変わっているだろうが、丁度ネットが普及してTwitterやWeiboが登場した頃に爆発的に広まった事件や言葉、ネット民達と当局の試行錯誤、当局に雇われてネット世論を操る「五毛党」当人へのインタビューの引用等等、話題豊富で今読んでも面白く変遷を辿る事ができる。2018/02/28
できっこないす
1
中国共産党の厳しい検閲下にあっても、ITツールに慣れ親しんだ80年代以降生まれの若者を筆頭に、時には執拗に、時には茶々を入れつつ、権力に決して屈しようとしない中国の若者達の様子が、豊富な事例を交えつつ紹介されている。2013/02/10
Junji Yogi
0
スキミング程度にパラパラ。「綱民」、「hold性」や「人肉捜索」など、これらの他にも現代の中国のネット社会を読み解くにおいて有用でありそうな言葉をたくさん収集する事が出来た。本格的に中国社会の研究に入る可能性がある今、避けて通る事が出来ないかも。そろそろ、ワ~も「綱民(ワンミン)」の一員になろうかな。アカウント作ろうかな^^2013/04/22
kozawa
0
中国のネット関連書籍を幾つか出して来たジャーナリストの2012年9月出版の本。2012/11/18