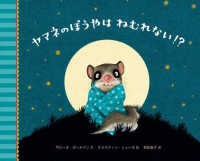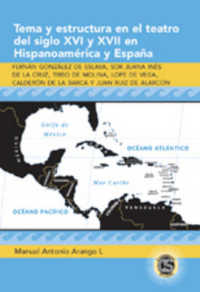内容説明
中国の近代美術はどのように展開したのか。「伝統」「新興」「国際化」の三つの視座から中華民国期の美術家・藝術運動を解明する。アジア遊学146号「民国期美術へのまなざし」の続編。
目次
1 伝統絵画の革新(「模古」の真意は何処に―金城の絵画と絵画論から;呉昌碩が日本にもたらしたもの―河井〓(せん)廬・長尾雨山を介しての伝播
呉友如と『点石斎画報』―ペン画と写真製版石印
民国期伝統版画―詩箋にみられる一側面―『北平箋譜』から『詩碑家詩箋譜』まで)
2 新興藝術の動向(前衛絵画の「代理戦争」―日中戦争におけるモダニズム絵画とプロパガンダ;魯迅とドイツ版画―メッフェルト、コルヴィッツの作品紹介をめぐって)
3 国際化と交流の流れ(日中洋画壇の架け橋―陳抱一;斎藤佳三と林風眠―知られざる東美校教授と国立藝術院院長の交友;傳抱石と日本―国境を越える美術史への手がかりとして)
著者等紹介
戦暁梅[センギョウバイ]
東京工業大学准教授。比較文化・日中近代美術史専攻。日中文人画の近代における変貌や日本人美術家の「満洲体験」など、近代日中美術の形成、変遷における「非西洋的」要素の究明を主な研究課題にしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。