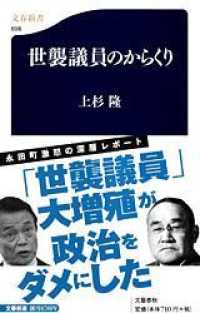内容説明
現代に生きるわれわれも一度は耳にしたことがある俄かに信じがたい言説のかずかず。近代日本において、何故、このような荒唐無稽な物語が展開・流布していったのか―オルタナティブな歴史叙述のあり方を照射することで、歴史を描き出す行為の意味をあぶりだす画期的成果。
目次
偽史言説研究の射程
第1部 地域意識と神代史(偽文書「椿井文書」が受容される理由;神代文字と平田国学;近代竹内文献という出来事―“偽史”の生成と制度への問い)
第2部 創造される「日本」(「日本古代史」を語るということ―「肇国」をめぐる「皇国史観」と「偽史」の相剋;戦時下の英雄伝説―小谷部全一郎『成吉思汗は義経なり』(興亜国民版)を読む)
第3部 同祖論の系譜(ユダヤ陰謀説―日本における「シオン議定書」の伝播;酒井勝軍の歴史記述と日猶同祖論;日猶同祖論の射程―旧約預言から『ダ・ヴィンチ・コード』まで)
第4部 偽史のグローバリゼーション(「日本の」芸能・音楽とは何か―白柳秀湖の傀儡子=ジプシー説からの考察;原田敬吾の「日本人=バビロン起源説」とバビロン学会;「失われた大陸」言説の系譜―日本にとってのアトランティスとムー大陸)
著者等紹介
小澤実[オザワミノル]
1973年生まれ。立教大学文学部准教授。専門は北欧史、西洋中世史、史学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
62
そうあってほしいという願望が、現実や史料事実を上回るとき、人は偽史を易々と受け入れてしまう。これが成長すれば、まちがった愛国心から人権や人命さえも押しつぶしてしまう。そんな歴史は洋の東西に関係なく繰り返されてきた。この論文集は江戸から現在まで、主に戦前において、偽史にロマンを求めるあまり、冷静に歴史を語らなかった事例についてのシンポジウムの記録である。編者が触発された先行の3冊とも私は既読であり、まさに趣味のツボが同じ。この世界はミイラとりがミイラにならないよう、しっかりと自戒しながら渉猟するべきだろう。2020/01/03
HANA
61
竹内文献、義経成吉思汗説、ユダヤ陰謀論に日ユ同祖論、日本人バビロン起源説にムー大陸。戦前、時代の徒花のように現れた珍妙な偽史だが、それは今なお奇妙な魅力をもって我々に迫ってくる。本書はそれら偽史を発生当時の状況や社会的影響等を元に分析した一冊となっている。特に竹内文献や日ユ同祖論、義経成吉思汗はある意味こういうテーマの鉄板だけど、内容や周辺人物だけではなく当時の社会状況と絡めて論じられているのは読んでいて新鮮。偽史の基本から発展まで、様々な角度から論じられておりどこを取っても興味深い所ばかりであった。2018/01/14
さとうしん
16
竹内文献、神代文字、義経=チンギス・ハン説、ユダヤ陰謀論、日猶同祖論、失われた大陸など、日本の偽史に絡むものはあらかた論じられているが、その多くが近代にあっては国策と関係していたのが見えてくる。『成吉思汗ハ源義経也』の小谷部全一郎がアカデミズムに対して反権威的にふるまう一方で、国家権力が自分の主張にお墨付きを与えることに対しては従順にふるまうというようなしぐさは、今でも割と見られるのではないだろうか。2018/03/06
ロア
11
論文集でした。そもそも問題になっている偽史をある程度知っている事が大前提となっているので、予備知識ゼロではとてもついていけない感じです。それは私です。2021/03/21
gtn
11
幼い頃、子供の科学本に源義経はチンギスハンだと書いてあったことを覚えている。この珍説は大正八年に日本陸軍の通訳官小谷部全一郎が唱えたもの。なぜ、こんな荒唐無稽な説が長らく支持されたのか。要は、うさん臭さを感じつつも国民は積極的に信じたかったのだろう。日本のヒーロー義経が兄に詰腹を切らされての最期とは辛すぎる。生き延びて、日本のみならずアジアの英雄になったのであれば溜飲が下がる。時局的に、戦意高揚にも利用されたか。2019/09/23