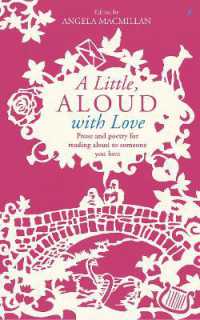- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
出版社内容情報
絵画や書、古文書など、紙や絹を用いた文化財は、表装によって、より美しく、より長くその存在を守られ続ける。
そして、これらの歴史的遺産を修理・保存し、伝えていくことは、そこに込められた人々の思い・願いをも共有していく営みである。
表装や修理は、どのような価値観や思想のもとに行われてきたものなのか。文化財の修理・保存の第一線にあり、その困難な作業の中で、技術者たちはどのような試行錯誤を重ねてきたのか。
残し伝えられてきた「モノ」との真摯な対話の中から、表装と修理にまつわる文化史を描き出し、今日の我々にとっての文化財保護の意義と意味を照射する。
内容説明
絵画や書、古文書など、紙や絹を用いた文化財は、表装によって、より美しく、より長くその存在を守られ続ける。そして、これらの歴史的遺産を修理・保存し、伝えていくことは、そこに込められた人々の思い・願いをも共有していく営みである。表装や修理は、どのような価値観や思想のもとに行われてきたものなのか。文化財の修理・保存の第一線にあり、その困難な作業の中で、技術者たちはどのような試行錯誤を重ねてきたのか。残し伝えられてきた「モノ」との真摯な対話の中から、表装と修理にまつわる文化史を描き出し、今日の我々にとっての文化財保護の意義と意味を照射する。
目次
第1部 現代の装〓・文化財修理(装〓師の声を聞く―技術者から見た装〓文化財修理の進化;表具師から装〓師へ;古文書修理の歴史と理念)
第2部 表装の文化史(日本中世の仏画の表装;“東山表具”の成立をめぐる小考;江月宗玩による表具の記録と制作;表装が伝えるもの―後水尾院縁の掛軸を事例として;近代日本における中国書画蒐集と表装;近代日本画の材料と表装)
第3部 修理の文化史(平安時代の仏画制作とその修理;前近代における書跡・古文書修理の諸相―現状維持の理念をめぐって;護持院隆光の寺社修理―元禄期の奈良を中心に;近代日本画の材料と表装;近世ヨーロッパ美術と修復―芸術作品の受容史の視点から)
著者等紹介
岩〓奈緒子[イワサキナオコ]
1961年生まれ。京都大学総合博物館教授。専門は日本近世史
中野慎之[ナカノノリユキ]
1985年生まれ。京都府教育庁文化財保護課を経て、文化庁文化財第一課文部科学技官(絵画部門)。専門は美術史
森道彦[モリミチヒコ]
1986年生まれ。京都文化博物館を経て、京都国立博物館研究員(中世絵画)。専門は日本美術史(中・近世絵画)
横内裕人[ヨコウチヒロト]
1969年生まれ。京都府立大学教授。専門は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。