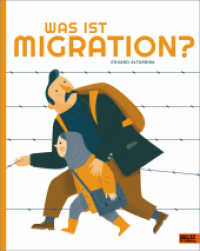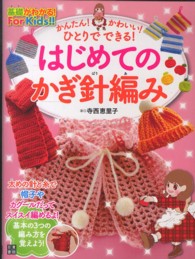内容説明
「地域情報マッピングからよむ東南アジア」とは、地域の“うごき”をよむ情報学の探究にある。そして、地域とは、自然環境、国家、政治、経済、社会、歴史、文化、慣習から住民の日常的な衣食住に至るまで、そこに生きる人びとの振るまいをも包含した、ダイナミクスの中に存在する「広がり」であると理解する。そこには、人びとの振るまいにみる“見えるうごき”と共に、人びとの考え方や行動の原点となる深層での“見えないうごき”がある。情報学の“眼”から地域情報のマッピング(写像)を介して、地域の“見えるうごき”と“見えないうごき”をよみ、その全体像を理解する研究モデルの構築に挑む。
目次
第1章 タイ語をよむヒトとコンピュータの“うごき”(タイ語とはどのような言葉か―タイ語ワープロの開発の動機;フィールド調査で学ぶ―タイ語ワープロの開発;タイ語音節をよむ―状態遷移論;タイ語機械翻訳の“夢”;タイ語『三院宝典』のコンピュータ総辞用例索引;言語を扱うコンピュータ―情報学の視点から)
第2章 上座仏教寺院と僧侶の“うごき”(東南アジア大陸部上座仏教の寺院と僧侶;タイ国における上座仏教;上座仏教僧侶の“うごき”をどのようによむか)
第3章 海域アジアにみるモノの“うごき”(情報学からみた中世・近世海域アジア交流;“HuTime”世界でみる暹羅国に回航した琉球船;階層型モデルでみる朱印船を港市国家アユタヤ;東南アジア産陶磁器と海域アジアのネットワーク分析;“HuTime”世界でみる「鎖国」下の唐船貿易;海域アジアを時空間概念と階層型モデルでよむ―情報学の視点から”)
第4章 ハノイ都市化の“うごき”をよむ(1873年以前と1940年以降のハノイ;フランス統治期の都市形成過程;自然環境と微地形分析―50年間の地形変化を探る;3次元景観モデル;リモートセンシングでみるハノイの都市化;都市をどのように解明しようとするか―情報学の視点から)
第5章 “見えないうごき”をよむ情報学(“HuTime”世界で歴史をよむ―長崎唐船貿易の事例;“HuMap”世界で災害をよむ―大坂三大大火と阪神大震災の罹災分析の事例;4D-GIS空間への展開―モデル化の方法と留意点)
著者等紹介
柴山守[シバヤママモル]
現在:京都大学東南アジア研究所・教授、専門:地域情報学、人文情報学。略歴:1947年京都府生まれ。1970年立命館大学理工学部卒業。工学博士(京都大学)。京都大学大型計算機センター、同大学東南アジア研究センターを経て、大阪国際大学経営情報学部教授、同大学大学院経営情報学研究科教授、大阪市立大学商学部・学術情報総合センター教授、同大学大学院創造都市研究科教授を歴任。2003年から現職。(社)情報処理学会山下記念研究賞(1996)、第2回日本モノつくり連携大賞特別賞受賞(2007)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
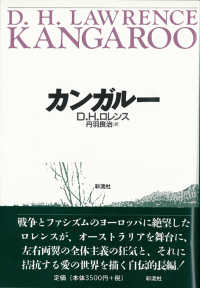
- 和書
- カンガルー

![YouTubeやネット動画をDVDにしてテレビで見るための本 〈2024-2025〉 - ダウンロードから編集・書き込みまですべて無料ツール [テキスト] 超わかるシリーズ](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866366869.jpg)