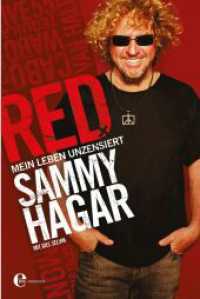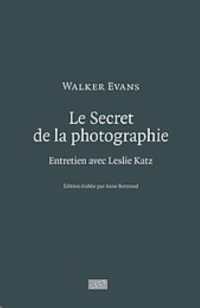内容説明
著者は、三十数年間、国語科の授業担当者として、「ことば」の問題を軸にすえ、教室の中の「私語」(わたくしことば)を挑発し、それをひろいあげ、できるだけ生身の人間としての「肉声」を伝えることをやってきました。本書は、そういう意味で、授業を仲立ちとして現われてきた学習者の姿を通して、世間に通用する価値観にあらがいながら、必死で自分の「ことば」を見つけようとし、自分を「表現」しようと格闘する若者像を、おとな・教員の側から描きだしたものです。今の学校制度のなかで、教員仲間との研究と協働によって、これだけのことはできるのだ、というギリギリの姿を、報告したものです。
目次
序章 学校をよみがえらせる着眼(子ども・若者の発語・沈黙をききとる力を)
1章 子どもの現実・「ことば」との格闘(登場人物に自分を重ねる―「山椒魚」「山月記」をとりあげて;流される「自分」に抗して―長田弘・日高六郎の評論などを通して;「現在」を問い「過去」を尋ねる―沢地久枝・阿部昭などの文章から)
2章 社会の現実・「ことば」による表現(日常を「事件」として捉える「生活体験文」;他者の世界に向き合う「聞き書き」;多様な学習を集大成する「インタビュー」;(補論)なぜインタビューか)
3章 学校の現実・「ことば」による解放(「声の文化」の復権―スピーチ活動の魅力;自己を解き放つ共同学習―汗と涙のルポルタージュ;(補論)表現学習の教材論・方法論・評価論(資料1・資料2)
総合学習の構想―教科の枠を越える授業の試み)