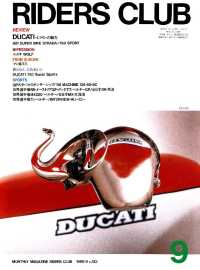内容説明
日本の近代化を牽引、世界の絹産業を支えた伝説の模範工場が、いま、世界遺産へ!写真や絵画、数々の史料で甦る、日本近代化150年の真実!奇跡の産業遺産がここにある。
目次
第1章 これが富岡製糸場
第2章 官営製糸場設立の背景
第3章 官営富岡製糸場の21年
第4章 民営化後の富岡製糸場
第5章 富岡製糸場を支えた工女たち
第6章 世界遺産へ!富岡製糸場と絹産業遺産群
著者等紹介
今井幹夫[イマイミキオ]
富岡製糸場総合研究センター・所長。1934(昭和9)年、群馬県甘楽郡南牧村生まれ。群馬大学学芸学部卒。富岡市内の小学校教諭、富岡小校長などを務め、95年富岡市立美術博物館長、09年より富岡製糸場総合研究センター所長。富岡製糸場誌・富岡市史編さん室長を歴任。南牧村誌、妙義町誌、富岡市史、安中市史編さんに携わる。長年の富岡製糸場に関する研究と活動がユネスコ世界遺産登録推薦に導いた功労者であり、各地での講演活動も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バニラ風味
16
9月に伯母二人を連れて、富岡製糸場に行きました。二度目の訪問ですが、ガイドさんによってお話しが多少違うので、もっと知りたくて読んでみました。以前、太河ドラマで見て、製糸場ができたのがゴールのようなイメージもありましたが、色々と大変だったんだなと判りました。これから行かれるる予定のある方は、さらっと読んでおくと役に立つかと思います。2016/10/22
C-biscuit
14
図書館で借りる。昨年の夏に富岡製糸場に行った。これといった予備知識なしに行ったので、漠然とした観光になってしまったのもあり、この本で復習する。冒頭に多くのカラー写真が載っており、現地の見所が網羅されている。現地に行ったが、見れなかった部分の紹介もあり、かなり詳しい内容である。特に時代とともに変わる製糸場があり、世界遺産に残す製糸場の意味がよくわかる。女工さんの給料や生活も紹介されており、昨今の女性活躍にもかぶる思いで読んだ。給料が当時の世間としてどうだったかなどの比較があるとわかりやすかったともに思う。2016/05/25
Sanchai
4
世界遺産登録から5日、海外出張での仕事がひと段落した後、息抜きで読んでみることにした。カラー口絵がふんだんに使われているので、富岡製糸場の見学前の事前学習にはちょうどいい。ただ、その他の絹産業遺産群の扱いは取ってつけたような感じだし、富岡で学んだ製糸工女さんたちがその後国に戻ってどう活躍したのかを、せめて岡谷あたりの話とつなげて書いてほしかった。じゃないと日本の近代化に果たした蚕糸業の役割を包括的に捉えたことにはなりにくいような気がする。横浜については辛うじて描かれているが。2014/06/26
まーや☆彡
3
予備知識無しで見学に行った人が「良かった」と言って帰って来たので気になっていました。行ってみたいです。あっさりとまとめてあって読み易いです。2014/06/30
nonchaka
3
まさに今、「旬」の本を図書館で見つけた。あー、大好きな近代建築の写真もたくさん載っていて、めちゃ、行きたくなった。明治以降の歴史の勉強にもなった。2014/05/07