内容説明
なぜ、女性たちは電車の中で化粧をするようになったのか。それは単にウチ・ソトの区別がなくなったからではない。化粧そのものが変わったのだ。今や化粧は、自己表現であり、立派な趣味の一領域であり、教養ですらある。「化粧が上手いですね」は褒め言葉であり、意のままに外見を操れる女性は「ビューテリジェンス」の持ち主として賞賛される。そして、コスメフリークたちの化粧への熱中ぶりは、まるでアニメやマンガに対するオタクのそれを思わせる。何しろ、彼女たちは私というフィギュアに「萌える」のだから。電車男と電車内化粧女。オタクとコスメフリーク。それは、九〇年代の日本社会が生み出した表裏一体の文化現象なのである。
目次
プロローグ 電車内化粧はなぜ非難されるのか
第1章 化粧のお仕事―「トータルライフ・アドバイザー」叶姉妹の謎を解く
第2章 化粧は人なり―「メーキャップ・アーティスト」藤原美智子の謎を解く
第3章 趣味は化粧―「カリスマ主婦」君島十和子の謎を解く
第4章 男より化粧が大事と思いたい―「さすらいの女王」中村うさぎの謎を解く
エピローグ コスメフリークという「オタク」―内面不在の一九九〇年代
著者等紹介
米澤泉[ヨネザワイズミ]
1970年生まれ。京都府出身。同志社大学文学部英文学科卒業。大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程単位取得。専門は化粧文化論、ファッション文化論。現在は、執筆活動とともに、化粧文化に関する講義を専門学校や大学で行っている。化粧文化研究者ネットワーク世話人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
GAKU
extrawhipcoco
寝落ち6段
サイバーパンツ
鍵窪錠太郎
-
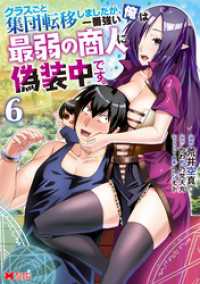
- 電子書籍
- クラスごと集団転移しましたが、一番強い…








