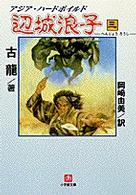目次
序論 相撲とは何か(「公認相撲規則」の構造;「相撲」の様々な輪郭)
第1部 相撲の歴史と技法の変遷(相撲の源流;相撲の成立 ほか)
第2部 現代相撲の技術的条件(現代相撲の基本的条件;相撲の技法の分析枠組 ほか)
第3部 変化の胎動(アマチュア相撲の成熟;相撲の国際化と技法の複雑化 ほか)
結論(相撲の将来像)
著者等紹介
新田一郎[ニッタイチロウ]
東京大学大学院法学政治学研究科教授。日本法制史・中世史専攻。自称「副専攻」として相撲史の研究も。東京大学相撲部長。昭和35年(1960)東京都生まれ。63年東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京大学大学院法学政治学研究科助手・講師・助教授を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。