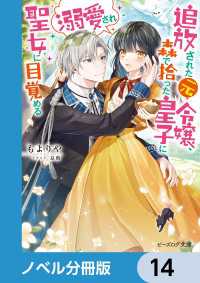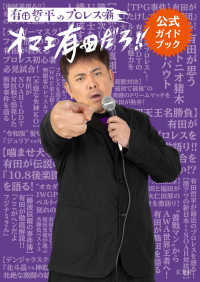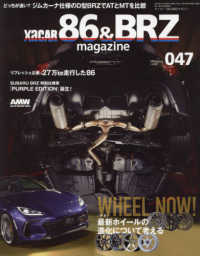- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
出版社内容情報
古墳時代に作られ、または渡来した遺物に注目し、モノから見える古墳時代の美を紹介。銅鏡、埴輪、工芸品、武具などを網羅的に紹介!
古谷 毅[フルヤ タケシ]
東京国立博物館主任研究員
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
37
古墳時代(約3世紀〜6世紀)の発掘品を美術の視点から。銅鏡や装飾品、武器などの金属製品、勾玉などのアクセサリー、多種多様なハニワ。そして、主役たる古墳の空撮。渡来物はともかく、レプリカなり発展型が作れたことは、技術と資源があり、それを維持できる経済と余裕は、後進を卑下することでなく、技術の発達の所以が当時の大陸の血みどろ具合に比べれば、「まほろば」にふさわしい世界があったのではないか。ハニワや意匠の美や工夫に費やすエネルギーを見ると、どうも古墳を作った人々が鞭でしばかれて苦役させたれたとは思えないのよね。2019/06/11
かりんとー
6
埴輪展後に。近所の古墳遺跡が意外と重要なものであると知り驚き。2024/11/03
ここ
3
弥生から古墳時代にかけてよく知れた。下げみづらは上、上げみづらは身分の下の人の髪型とは。あと勾玉が背中合わせの立花に惹かれた。飛鳥時代位から文化的になるイメージだけど、全然。ずっとゆたかだったし高度な生活があった。家の形、格好いいなぁ。日本人の服装や文化って本当はここにあるものかもなって。左袷になる以前のに。なのに全然詳しくない今が寂しい。陵の形の意味さえ解らないんだものね。鳥居形はいつ現れたんだろうなぁ。謎は尽きぬ。2018/08/23
暇人
2
古代の権力者は何故こんな奇っ怪なものを作ったのだろうか?最新技術をもつ渡来人らを駆使したのだろうが、スピリチャルな神秘性を感じる。機械のない中、手作業でよくここまで精巧に作れたものだ。2017/04/01
やま
2
古墳時代を美術の観点から幅広くみています。古墳時代も大陸からの技術や文化を日本的にしていたことが面白い。古墳から遺物までいろいろありますが、昔からサルの埴輪がかわいくてお気に入り。2017/03/11