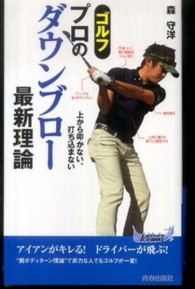出版社内容情報
《概要》
なぜ私たちはAIの活躍を目にしたとき、楽しさばかりでなく「不気味さ」を感じてしまうのだろうか? 私たちにとってAIとは何なのだろうか? ――AIと暮らすことが当たり前となった今、「AIとは何か」を美学の視点から問いかける。
『2001年宇宙の旅』のHAL9000、怪物フランケンシュタイン、映画の中のゾンビ、『火の鳥』のロボットたち……誰もがおなじみのフィクションに登場する「人間でない存在」から、「シンギュラリティ」や生成AIを利用したアートまで、カント哲学や実存主義を手がかりにAIの「面白さ」を考える1冊。
「人は必要性や有用性だけから何か新しいものを作り出したりしない。面白いから作るのである。
人工知能の場合もこれと同じだ。多くの場合、AIの有用性や効果――ポジティブにせよネガティブにせよ――についての議論ばかりが目立って、その面白さ、「遊び」的な側面についてはあまり語られない。遊んでいる場合ではない、そんな気楽な話ではない、ということだろうか。しかし私はせっかくAIについて本を書く機会をいただいたので、ここでは思い切り気楽に面白く語ってみようと思う。」
(第一章「幽霊はどこにいる」より)
《目次》
まえがき
第一章 幽霊(ゴースト)はどこにいる ――AIをめぐる、別な語り(ナラティブ)
第二章 私もロボット、なのか ――本当は怖くないフランケンシュタイン
第三章 不気味の谷間の百合 ――不気味の谷間の百合
第四章 実存はAIに先立つ ――人工知能の哲学、ふたたび
第五章 現代のスフィンクス ――人間とは何か?とAIは問う
あとがき
《著者紹介》
吉岡洋(よしおか ひろし)
1956年京都生まれ。京都大学文学部哲学科(美学専攻)、同大学大学院修了。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)教授、京都大学大学院文学研究科教授、同大学こころの未来研究センター特定教授を経て、現在京都芸術大学文明哲学研究所教授。専門は美学・芸術学、情報文化論。著書に『〈思想〉の現在形──複雑系・電脳空間・アフォーダンス』(講談社選書メチエ)、『〈こころ〉とアーティフィシャル・マインド』(共著、創元社)、『情報と生命──脳・コンピュータ・宇宙』(共著、新曜社)などがある。
内容説明
SF映画やマンガで、私たちはロボットや人工知能が活躍する物語に魅せられてきた。現実の世界でも、生成AIをはじめ人工知能はごく身近なものとなっている。今、あなたはAIのことをどう感じているだろうか?心躍る楽しい技術?それとも、違和感や不安を抱かせる存在?私たちにとって、AIとはいったい何なのだろうか?「不気味さ」「騙されるということ」「身体性」…これらの視点を手がかりに、AIを美学の問題として考える。
目次
第一章 幽霊はどこにいる―AIをめぐる、別な語り(私たちにとってAIとは何なのか?;遊びとしてのテクノロジー ほか)
第二章 私もロボット、なのか―本当は怖くないフランケンシュタイン(技術が人の姿で現れる;素顔の「怪物」 ほか)
第三章 不気味の谷間の百合―賢いハンスたちと共に(フランケンシュタインとゾンビ;「不気味さ」とは何を意味するのか? ほか)
第四章 実存はAIに先立つ―人工知能の哲学、ふたたび(人工知能とは哲学の問題である;ドレイファスのAI批判 ほか)
第五章 現代のスフィンクス―人間とは何か?とAIは問う(ロボットの娘とAIアイドル;AIの制作した「作品」の意味 ほか)
著者等紹介
吉岡洋[ヨシオカヒロシ]
1956年京都生まれ。京都大学文学部哲学科(美学専攻)、同大学大学院修了。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)教授、京都大学大学院文学研究科教授、同大学こころの未来研究センター特定教授を経て、現在京都芸術大学文明哲学研究所教授。専門は美学・芸術学、情報文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
榊原 香織
izw
愛楊
mitarashidan5
-

- 和書
- 口外禁止