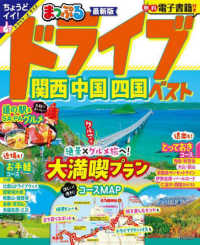出版社内容情報
かつて中国東北部に建てられた日本の傀儡国家・満洲国。その実態は謎が多い。しかし、最新の研究に基づき、中国大陸における漢民族と満洲族、そして日本の軍部と政治派閥それぞれの立場、満洲国の存立基盤そのものである経済の実態、満洲国内の新聞・文芸・映画などの活発な活動に光をあてることで、ついに、その詳細な全体像が明らかにされてきた。
異なるナショナリズムの交錯が生んだ国家とは。東アジアに存在した異形の国の実態に迫る。
内容説明
かつて中国東北部に建てられた日本の傀儡国家・満洲国。その実態は謎が多い。しかし、最新の研究に基づき、中国大陸における漢民族と満洲族、そして日本の軍部と政治派閥それぞれの立場、満洲国の存立基盤そのものである経済の実態、満洲国内の新聞・文芸・映画などの活発な活動に光をあてることで、ついに、その詳細な全体像が明らかにされてきた。異なるナショナリズムの交錯が生んだ国家とは。東アジアに存在した異形の国の実態に迫る。
目次
序章 いま、なぜ、「満洲国」か
第1章 なぜ、満洲だったのか
第2章 建国の綻びを解く
第3章 建国はしたけれど
第4章 産業開発から戦時体制の構築へ
第5章 敗戦、そして戦後
著者等紹介
鈴木貞美[スズキサダミ]
1947年山口県生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。国際日本文化研究センター及び総合研究大学院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
68
満洲国の成立史や政治的な動きについては、本書だけでは物足りない。やはり緒方貞子の博士論文とか、中公新書の『キメラ』は併読しておきたい。むしろ本書の魅力は、その短い歴史を時期ごとに細かく区切り、そこに様々な文化的な動きを丁寧に組み込んでいること。それも文学と現地の同人社会、軍歌を含む音楽、映画などで、特に映画は世界の趨勢の中に位置づける視点もあり興味深かった。巻末の詳細な人名索引もありがたい。戦後日本で活躍した満洲生まれの人たちの名前を見ると、その苦労が作品のそこここににじみ出ているのが分かる。2021/08/14
MUNEKAZ
17
文化面から見た満洲国史といった感じだろうか。通史の間に満州国を訪れた文人や映画人、知識人らの視点が挟まる構成。「五族協和」のスローガンがあり、日本とは別の国家というタテマエがあった満州国は、一概に台湾や朝鮮と同じ「植民地」というくくりで見るには捉えきれない部分があるのかも。美しい理想と傀儡国家という現実で苦悩する日系大学生のエピソードは、満州国の持つ矛盾を鋭く抉っており強く印象に残る。ただ事実の羅列が続くというか、全体的にまとまりなく感じる部分もあって、ある程度知識をつけてから読む本だとも思う。2023/06/04
nagoyan
16
優。詳しい感想は後日。ただ、面白かった。特に4章末尾の森崎湊のエピソードは。(以下4月18日追記)「満洲国」を単に日本帝国主義の傀儡国家と片付けてしまわずに、その「建国」の尽力した、日本側、中国側の勢力の意図を丹念に追う良著。全体的印象は多少、左翼的な公式史観に対する異議申し立てという感もあるが、修正主義とは一線を画そうとしている。「五族協和」の「理想」が、中国民族主義の攻撃を受け、他方で日本側支配層の場当たり的・ご都合主義に搔きまわされ、腐食していく。地に足のついていない理想主義の空疎さが痛々しい。2021/03/04
さとうしん
16
満洲国の通史的な解説に加えて文芸・映画・思想・学術など文化面に着目しているのが特徴だが、内容的に中途半端になってしまった感がある。ナショナリズムと文化面に全振りしても良かったのではないか。冒頭の「でっちあげ」に関する議論も、計画性という面ではその通りだが、物事は単純化できないという以上の話にはならず、さして意味のある議論とは思えない。2021/03/03
しんい
14
歴史・政治・経済の先生による書籍とは異なり、文学の面から満州国に向き合われているため、視点が他の書籍とは異なる面が良い。その分、論を補強するための客観的指標としての経済指標や統計データは極端に少なく、また話があちこちに分散し前後もする編集方針から、新書として読みにくいことも事実。それでも満洲国・朝鮮・台湾でそれぞれ異なる統治方針がとられていたこと、「傀儡政権」でも旧清朝皇帝を戴くことを反映し、満洲国の事業として孔子廟での儀典が行われていたことなど、あとからつなぎ合わせたストーリーにはない価値がある。2023/03/12
-
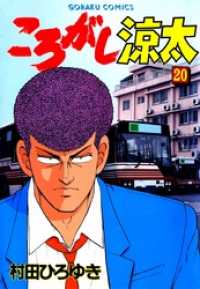
- 電子書籍
- ころがし涼太 20