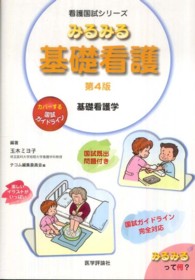出版社内容情報
福島原発事故後も存続が図られる、産官政学メディアが癒着した巨大利権・原子力村。原発関連記事で知られる筆者が描く、ムラの実態。
【著者紹介】
朝日新聞経済部記者
内容説明
一匹の化け物が日本を徘徊している。「原子力村」という名の化け物が―。電力会社、産業界・財界のみならず官僚、政治家、学者、さらにはマスコミすら取り込み、この「化け物」は半世紀以上にわたって肥大化してきた。そして、福島第一原発事故以降も必死に原発延命を図り、民意を無視した再稼働を進めている。原発関連取材の第一人者として知られる記者が巨大な利権複合体にメスを入れる。
目次
プロローグ 事故後の反省記事
第1章 「村」に切り込む
第2章 強大な利権構造
第3章 「国策」の果てに
第4章 4人の経産官僚
第5章 残る原発のごみ
第6章 買われたメディア
著者等紹介
小森敦司[コモリアツシ]
1964年東京都生まれ。上智大学法学部卒業。87年、朝日新聞社入社。千葉・静岡両支局、名古屋・東京の経済部に勤務。金融や通商産業省(現・経済産業省)を担当。ロンドン特派員(2002~05年)として世界のエネルギー情勢を取材。社内シンクタンク「アジアネットワーク」でアジアのエネルギー協力策を研究。現在はエネルギー資源・環境分野などを担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hatayan
44
朝日新聞の記者が「原子力ムラ」と呼ばれる産官学とメディアからなる原発推進の複合体に迫るルポ。青天井で経費がかかっても後戻りできない国の事情で強引に進められる核燃料サイクル、原発ゼロを支持する世論を逆撫でするように原発推進に回帰する自民党政権など。2020年に読んで目を見張ったのは、安倍政権の最側近の今井尚哉秘書官が経産省時代に原発推進の当事者だっただけでなく、叔父が元経団連会長で原子力産業協会会長の今井敬氏であったこと。全体を通して、原発が生む核のごみという負の遺産の処理を先送りにしていることを憂えます。2020/09/10
rico
35
再読。読了登録をしようとして、気づくという…(-_-;)感想は初読の際と大きく変わるものではないが、政官財学&メディアががっつり組んで推進している原発という大規模プロジェクトは、それによって利益を得ている人が国を動かしている限り、民意がどうあれ方向転換できなくなっているのかもしれない。原発の維持に注いできた人的・財務的資源の3分の1でも別の方向に使っていれば、この国の姿は全く違ったものになっていたのではないか。2019/03/19
coolflat
13
特に目新しい記述はない。参考になったのは、モンゴルの最終処分場に関して。モンゴルの最終処分場とは「日米が共同で、モンゴルに使用済み核燃料などの最終処分場を造る計画」の事だが、これは溜まりに溜まった日米の核廃棄物をモンゴルに最終処分する事ではない。この計画はいわゆる「包括的燃料サービス」の事で、例えば、日本がA国に原発を輸出する。そのA国にモンゴルがウラン燃料を輸出する。使用済み核燃料は再びモンゴルに戻す。ーという継続的なシステムの事だ。要はモンゴル起源のウランでなければ、モンゴルは核廃棄物を引き取らない。2016/09/28
skunk_c
11
朝日新聞の記者が自身の記事をまとめながら、所謂「原子力村」に迫る。あの未曾有の事故があっても解体できない実態を、経産省と電力会社、そして関連企業の巨大な利権構造から解き明かそうとする。そこに自社も含めたマスコミが絡め取られていく様子や、TCIA(東電のCIA)が反原発派の個人情報を収集するなど、背筋の寒くなる話が続く。さらに国内の原発を止めながら一方で海外輸出を進める民主党政権や、経産省若手職員が核燃料サイクルに反旗を翻したあと左遷されていく様子など、「大きすぎてつぶせない」核燃サイクルの恐ろしさも。2016/03/21
rico
9
積読の山から発掘。朝日新聞の記事を再編集したもの、ということで断片的な印象は否めないが、「官」だけでなく、産業界、さらにはマスコミや広告業界の事情などにも言及し、社会にがっちり組み込まれている「原子力村」の実相を伝える。事情通の知人からきいた、国が原発が安価で環境への響も少ないという計算方法を緻密に構築した結果、方針転ができなくってしまったという話を思い出した。異論を封じ、ひたすら再稼働を進める状況にはため息しか出ない。2017/09/03
-
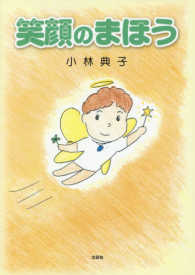
- 和書
- 笑顔のまほう