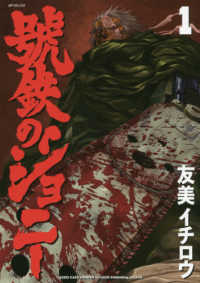出版社内容情報
時とともに変わる風景。今ある緑は、どんな経緯を経て生まれたか。その景観に人はどのように関わってきたか。
内容説明
風景は時とともに変わる―。原生林も太古から変わらぬ姿と思いがちだが、気候の変化や災害などで、植生は違った状況になる。人工林や雑木林も、人がどんな手を入れるかによって生える木の本数、樹形、下草の植生が変化する。そんな森林景観に日本人はいかに関わってきたか。今ある緑はどんな経緯を経て生まれたか。現代につながる森と人の歩み。
目次
第1章 「日本の原風景」の嘘(パッと散るサクラの欺瞞;鎮守の森は神聖だったのか ほか)
第2章 ニッポン林業事始(林業誕生は邪馬台国から;古代の都が奪った巨木の森 ほか)
第3章 近代国家は林業がつくった(岩倉使節団の見たドイツの森;国有林をつくった「夜明け前」の時代 ほか)
第4章 森林景観は芸術になりうるか(森を求めて歩く市民たち;『日本風景論』と学校林 ほか)
第5章 緑あふれても消えた美しい森(消えたアグロフォレストリー;「海で採れた木」が森を変えた ほか)
著者等紹介
田中淳夫[タナカアツオ]
1959年大阪府生まれ。静岡大学農学部林学科卒業。出版社、新聞社等を経て森林ジャーナリストに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
68
こういう本こそ読まれてほしい。日本の国土の3分の2は森林。日本人は古来より森を、木々を大事にしてきた、その結果だ……と思いたい。 が、実態はまるで違っていた。676年に天武天皇が飛鳥川流域の伐採禁止令を出していたとか、そもそも古墳を作るためには、周辺の木々を相当伐採したのだろうと思える。度重なる都の移転は、いろいろ理由はあったようだが、その一つには、周辺の森の木々を伐採し尽くしたこともあったようだ。2017/07/30
翔亀
56
日本の森林史、それは卑弥呼の時代から人間の手が加わり完伐(=禿山化)と植林或いは再生の繰り返しだから、林業史に他ならない。体系的でないのが残念だが、森林の姿(=日本の風景)が如何に変えられてきたかが良く分かる。大まかに言って、日本の森林は江戸時代の前に丸裸→江戸時代に再生→明治に丸裸→その後試行錯誤→戦後しばらく丸裸→現在は最も豊か、とされる。これに、森の質の話が加わるので一筋縄に行かない。明治以降の林政史が国家経営の根幹とされたわりには(だからこそと言うべきか)変転を重ねて来たことを知り唖然とする。2016/11/24
かつどん
15
日本人は森林と上手に寄り添って暮らして…といったざっくりイメージは、消え去った。後先考えずとりあえずやってしまおう的な面がここでも表れてたのだなと感じる。一部素晴らしい技術伝承されていただけでも救いだ。今は国産は増えたので使い時なようだ。多種多様を美しさの最良とした時、ハインリッヒ・ザーリッシュの 「美しい森林をつくる事と、人工林で経済的な利益を追求する事は調和する」「技術的合理性のある森は最高に美しい」という言葉は、自然と都市がどう寄り添うか、また都市構造そのものの今後のデザインへのヒントと成り得る。2017/04/16
しゅわっち
10
現状の森林をみて、安定していると思っていた。しかし、エネルギー、建築資材に使い危機的状態がいくつも有ったことを知った。経済状況により、時代のうねりに翻弄された状態がわかった。また、技官より文官を上位にする状況をGHQに指摘され、修正したが、最近復活したことを知った。結局、東大法学部の圧力が、予算に押し切られた状態を感じる。官僚支配を政治で解決してもらいたと思うのは、私だけだろうか。2018/11/23
my
7
日本の森との関わりの1500年の歴史を駆け足で解説。感想としては、日本って森の使い方が昔から下手だったんだなぁということ。太古の昔から木を大量に伐採しては禿げ山にして、後悔して植林し、植林した人の精神が褪せてきた時にまた大量伐採し禿げ山にして後悔する。。。西洋との比較はあまり好きでは無いですが、やはりドイツやスイスと比べると、余りにも先人たちの思いや願いを無視して刹那的に行動している印象を受けました。2017/02/07