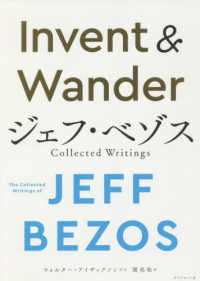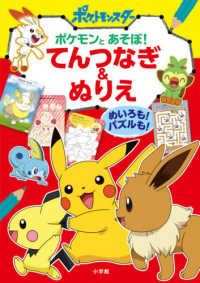出版社内容情報
単身者はどんどん増え、2050年には4割に達する。介護も問題だが、誰かに看取ってもらえるのかも大きな問題だ。安心して最期を迎えられる社会はどうすれば可能か。その仕組みを提案する。
内容説明
急増する孤独死、深刻化する無縁社会…。人が看取られ、弔われるということは、もはや当然のことではなくなっている。死後を託す人がみつけられない人々を支え、他者とともに生きる「生」を取り戻すために私たちが今なすべき選択とは何か。「跡継ぎ」が不在の時代に、社会で死を受け止める道を模索する。
目次
第1章 死後の安心システムの崩壊(墓と葬儀の変化;変化の背景となる社会の「個人化」)
第2章 国家と葬送(国が想定する葬送の担い手;「ライフエンディング・ステージ」の提案 ほか)
第3章 市民、自らを助く(生前契約「りすシステム」の誕生;そのほかの生前契約実施団体 ほか)
第4章 「弔われる権利」とその担い手(葬送の社会化と「弔われる権利」;「弔われる権利」という概念 ほか)
著者等紹介
星野哲[ホシノサトシ]
1962年東京生まれ。朝日新聞社で学芸部記者、社会部記者、電子電波メディア本部次長、CSR推進部企画委員などを経て、現在教育企画部所属。立教大学社会デザイン研究所研究員、エンディングデザイン研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
20
下手すると課題の指摘だけに終わりがちなネタだが、予想外にとても前向きな本でよかった。◇「死ぬほうも見送るほうも家族が主体」、それを当然視していたのがこれまで。それでは不具合のほうが大きくなっているのは、子育てや介護と同じ構造の課題だ。それに応えようと各地で始まっている「協セクター」「選択縁」が主体となった取組を追い、新たな弔いの形を皆で作っていこうと呼びかける。◇檀徒(≠檀家)」という個人主体の制度が興味深い。他のケア分野とちがって、我々の社会は「寺」というすごい資産を持っている。活用しない手はないよな。2014/04/12
Ayumu
7
お一人様の終活が気になり読了。著者の修士論文がベースになっているそうで、多くのデータ、事例、文献が紹介されている。家族の形態が変化している中で、当然、墓、葬儀についても変化しており、もっと積極的に考えていくべきことのように改めて感じさせられた。著者が言っているように、死の不安がなくなることで、今日をもっと充実させられるように思います。2021/06/19
kaz
2
孤立死や「おひとりさま」の終活が主たるターゲットのように見えるが、前半部分はむしろ終活そのものの考え方について深い洞察が示されている。終活全般をしっかり考えるうえでは、一般的な終活のノウハウ本よりもはるかに役に立つ。ただし、まとめの部分はNPOによる生前契約システムの意義を強調したいがあまり、論旨展開に飛躍があるように思える。後半はあくまで著者の思いとして読むべきなのだろう。2020/04/01
Stella
2
生涯未婚者の増加による「家族に葬儀・埋葬をお願いできない」時代到来に対する模索。 エンディングノートのような話かと思ったら骨太。2014/03/25
てくてく
2
少子高齢化にともない誰かに看取られ、死後の諸手続きを行ってくれる人が少なくなり、誰もが自分の老後や死について考える必要があるが、従来の血縁に頼らない方法を支えるシステムにはどのようなものがあるのか検討した本。類似テーマの本をこれまでに読んでいることもあり、既読感のある情報が少なくない点は残念だったが、現状を整理しているという点では役に立った。2014/03/03
-
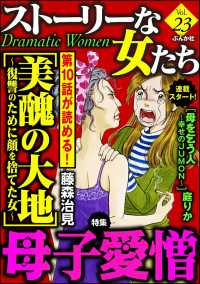
- 電子書籍
- ストーリーな女たち Vol.23 母子…