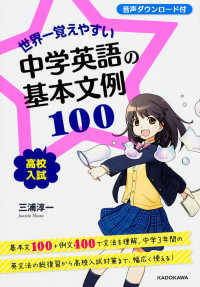出版社内容情報
戦国大名の概念については混乱が生じ、未だ解決されていない。1980年代以降、急速に進展した研究成果を集約、その全体像の概要をまとめ、戦国大名の新しい基本文献として提示する。
内容説明
飢饉と紛争が相次いだ戦国時代、戦国大名はどのように生まれ、地域国家の秩序を成立させたのか。大名家と家臣団の在り方から戦争にいたる背景まで、領国経営に必要な要素を検証する。また江戸時代へと向かう中での大名の変容をも視野に入れ、その統治構造をわかりやすく解説する。
目次
序章 戦国大名の概念
第1章 戦国大名の家臣団構造
第2章 戦国大名の税制
第3章 戦国大名の流通政策
第4章 戦国大名の行政機構
第5章 戦国大名と国衆
第6章 戦国大名の戦争
終章 戦国大名から近世大名へ
著者等紹介
黒田基樹[クロダモトキ]
1965年生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。博士(日本史学)。専門は日本中世史。現在、駿河台大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
軍縮地球市民shinshin
11
戦国大名の権力構造(家臣団・税制・流通・行政・国衆・戦争)について、著者が専門とする後北条氏や武田氏を事例にしながらまとめた概説書。かつての高圧的な統治を行っていたと思われていた時代の戦国大名とは違い、後北条はかなりシステマティックに統治していたことが分かる。江戸時代の幕府や大名統治の原型をみるような感じだった。個人的には戦国大名と国衆の違いは興味深かった。ただし後北条は戦国大名の中でもかなり先進的な事例だったかもしれず他大名はどうだったのか明らかにされていない。史料が残っていないというのもあるのだろうが2016/08/30
Toska
10
何度目か。新書サイズだが骨太な一冊。「戦国大名はなぜ戦争をするのか」という問題に真正面から取り組んでいるのが大きい。それは当たり前のように見て、実は全然当たり前ではなかった。人々の「自力救済」を封印することで、戦国大名領が一種の平和領域として機能しながらも、他の大名との対外戦争は寧ろ大規模化する一方だったという大いなる矛盾。2022/01/15
nizi
5
著者の専門性から後北条氏を例にとっての解説が多い。四方、行政、軍事と分けて書いてあるため、知りたいことをピンポイントで探すことができてとても良かった。後北条氏にはない、他地域特有の例があるなら読んでみたくなった。2025/01/01
珈琲好き
5
よくできてるシステムだよなぁ。個人の把握まではできてないけど、近代国家とそんなに遜色ないんじゃね?2016/10/22
スー
5
学校で習ったのは何だったのだろう?織田家も豊臣家も革新的ではなく北条家でも重要な流通路や国境以外の関所が撤廃されていた。国衆は小型の大名で独自の経営を行っていた。大名家に庇護してもらう代わりに上納金を払っていて頼りないと感じたら他の大名に鞍替えしていた。大名が頼りないと評判が立つと国衆が離れてしまうので彼等を繋ぎ止める為に必至だったのが分かる。武田家が呆気なく滅んだのが理解できた。2016/10/06


![ジャズ・ギター・アドリブ・マスター・ブック[演奏動画連動版] - 運指でジャズの音使いをマスター!!](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42851/4285154625.jpg)