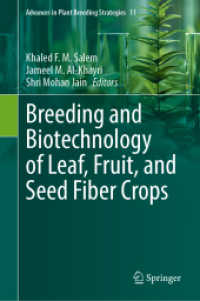出版社内容情報
将棋はいったいいつごろから遊ばれていたのか? 中国から伝わったのか、それとも別のところからか? など、まだまだ解明されていない謎多き将棋の歴史について、最新の研究成果を発表する。
内容説明
将棋の歴史は、いまだ解明されていない謎が多い。これまでは、漠然と中国から伝えられたと思われてきた。しかし、中国の将棋(象棋)と比べてみると、駒の形、その進め方、将棋が始まったとされる時期など、多くの違いがあるのだ。では、いったいどこから将棋は伝わったのか。そして、どのように変化し、複雑で面白い遊びとして、広く日本に定着したのか。最新の研究成果とともに、近年の将棋熱を探る。
目次
序章 将棋伝来の謎を探る
第1章 中世に栄えた将棋の源流
第2章 職業として認められた江戸時代
第3章 宗家一二代「大橋家文書」による真実
第4章 近代化がもたらした繁栄と衰退
第5章 戦後の復興から未来へ
著者等紹介
増川宏一[マスカワコウイチ]
1930年長崎市生まれ。世界各地をフィールドワークしながら、将棋史、盤上遊戯史、賭博史の研究を続ける。遊戯史学会会長、将棋博物館元顧問。大英博物館リーディングルーム・メンバー、国際チェス会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はじめさん
27
本邦の将棋史を紹介。世界に数多ある将棋のルーツは、古代インドのチャンドラ。元は4人制と思われたが2人制が本家本元すごいね、ガンジス! / 囲碁の方が大陸からの伝来は古いが、将棋は朝鮮や中国と陸路経由ではなく、どうも海ルートできたらしい。玉金銀桂香は宝石や香木の事。安い駒と高い駒を交換するジャイアニズム海洋貿易ゲーム。駒が五角形なのは卒塔婆モチーフで、僧侶等の知識階級が嗜んでいたのが、武家にも伝染。2013年の本だが、プロ入り前のカロリーナにも言及。だが、4年後に50年に1度の天才少年棋士が光臨するとは…。2018/06/09
Book Lover Mr.Garakuta
16
図書館本:将棋に関する歴史の話、将棋の起源であるチャトランガ(インド北部のマウカリ王朝期)のルーツから始まり、どの様に日本に伝来し、現代将棋になったのかと言う歴史と変遷の解説がのせられている。2021/02/13
ニック肉食
3
江戸時代の話は面白かったです。2018/06/02
ひみーり
3
私は新書をほとんど読まないのですが、この本は4日で読み終わり、最初から最後まで楽しく読めました。私は歴史にほとんど興味なく、つねに最新のニュース最新のテクノロジーと新しいことにしか関心を示さなかったのですが、昔から今までと歴史の積み重ねで今があるのだと、歴史は人間の今までの生きた証だと思い、これからは歴史物も少しずつ読んでいこうと正直思いました。将棋は囲碁と違いハンデがしづらいゲームだと思っていたのですが、実はそうではなくハンデをしても確りゲームとして成り立っているのだと、本を読んで印象を受けました。2015/06/23
kokada_jnet
3
「民衆史観」もここまで徹底すると凄いね。過去の著作同様、江戸時代では家元配下の有段者がどのくらいいたかとかを、延々と語っているし。戦後編でも、連盟配下の支部について語ったり、レジャー白書での将棋人口の数ついて論じたりして、プロ棋界の話は最小限だけ。2013/03/11