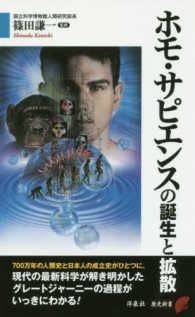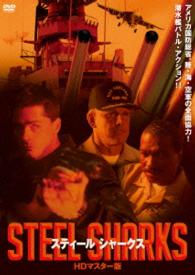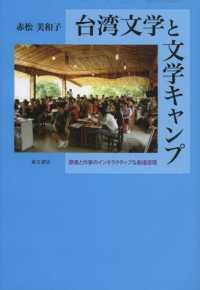内容説明
1910年、大日本帝国自立の犠牲として同時並行的に生起した大逆事件と韓国併合。天皇制国家の理想は植民地主義的想像力と結びつき、日本人の境界を規定する排除/内包の構造を創出した。その衝撃から産み落とされた「日本語文学」を再読し、事件から百年の今、国民国家のフィクションを暴き出す。日本人、在日朝鮮人、被差別部落民、引揚者たち―「日本人」とは誰なのか。
目次
第1章 「日本人」と「国語」のドラマトゥルギー
第2章 危機の時代の夏目漱石
第3章 永井荷風と谷崎潤一郎
第4章 植民地朝鮮と“日本人”
第5章 大逆事件と被差別部落
第6章 明治期日本の「理想」と「虚構」
第7章 戦後に“在日”する根拠とは何か
第8章 北海道という「植民地」の発見
第9章 三島由紀夫と大江健三郎の「大逆」
著者等紹介
高澤秀次[タカザワシュウジ]
1952年北海道生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。文芸評論家。現在、二松學舎大学文学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みなみ
11
おおむね大逆事件にまつわる本かと思ったのだが、実際には(目次をみればすでにわかるように)文学者の作品のなかにある戦争や植民地といった政治的問題を解き明かしていく本。扱われる時代は明治から戦後民主主義まで幅広い。自分として、取り上げられた中では読んでるほうの夏目漱石のくだりが一番なるほどと思った。2020/11/30
浅香山三郎
5
偶然であるが、大澤真幸さんの「不可能性の時代」の概念が本書の組み立ての一つの軸になつてゐる。近代の日本の帝国化の犠牲となつた、大逆事件と韓国併合といふ二つの出来事から100年の間、文学や文学者が表現した「近代」あるいは「帝国」「天皇制」の歪みを指弾した流れを追ふ。4・5・7章で扱はれた、在日の文学者たちの日本語文学、植民地育ちの日本人小林勝による視点、金時鐘・梁石日らと日本文学の比較(SF、開高健)が興味深い。「近代」と「戦後」から排除された文学への無知に対する、著者のある種の怒りを感じた。2016/02/13
たらら
4
1910年の大逆事件、韓国併合から100年、三島自決から40年──というだけなら思い付きの企画だが、これは拾いものの力作。1910年の二つの出来事が明確に国民国家・日本を形作り、その結果産まれた内・外に、文学がどう反応してきたかを辿る。佐藤春夫、夏目漱石、谷崎、小林勝、井上光治、中上健次、ヤンソギル、開高健、小松左京、三島由紀夫から村上春樹、大江健三郎へ。きわめて軸のしっかりした読解に目が洗われる。2010/11/23
ムチコ
3
漱石の登場人物の匿名性についてとか、村上春樹と三島との関係性とか、個々の(特に前半の)視点は面白かったんだけど、全体の見取り図がないような構成で「結局なんの話だったんだっけ」となるのが残念。2020/10/19
しゃっと
2
「歴史は繰り返す」という命題を史実に則って展開。「日本人」という帰属意識がなかった明治初期、日本人以外(「非国民」、朝鮮、琉球、アイヌ、部落民等)を規定することによって、「日本人」とは何かを炙り出していった。大逆事件をこういった文脈の中で考える視点が新しかった。日露戦争後、大逆事件前の閉塞感は、帝国という「理想」を追い求めながらも、アイデンティティさえあやふやという「現実」の挟み撃ちによるものということか。こういった時代性を考慮し、『それから』を再考すると、やはり漱石の慧眼に敬服せざるを得ない。天才だ2020/06/01