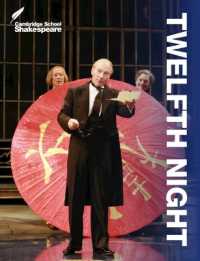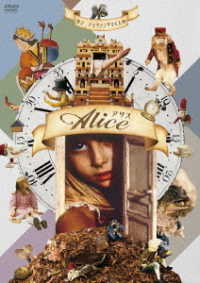内容説明
戦後文学のなかにあって、あたかも「魔の山」のごとく神秘に身を包んで屹立する埴谷雄高の文学。その難解な意匠と沈鬱な気分のうちに、いかなる思想的なポテンシャルがあったのか。「自同律の不快」という「前‐存在論的根本気分」のリアリティが、存在についての問いを読者の内に喚起し、「存在の革命」へと誘導する。そこに、埴谷雄高の文学の未完の可能性を見出し、同時にその隘路をも発見しようとする。「存在論」という切り口から埴谷文学の魅力と限界を鮮やかに画定し、新たな「精神のリレー」へと読者を誘う瞠目すべき埴谷雄高論。
目次
第1章 『死霊』の懐胎―獄中にて
第2章 「存在への平手打ち」へ―『不合理ゆえに吾信ず』
第3章 虚体論とその射程―初期の『死霊』から
第4章 「存在論」の隘路
第5章 死者の贖いの問題―“夢魔の世界”の意味するもの
第6章 遺された『死霊』の可能性
-

- 和書
- アナウンサーは足で喋る
-

- 和書
- 子どもの精神力 国民文庫