出版社内容情報
流行りのマインドフルネスの原点でもある禅のそもそもから歴史、基本の教え、坐禅法、現代での活用術などをやさしく説く。学校や社会生活で生かせる禅の知恵を知る一冊。
内容説明
坐ると何が変わるの?禅がいま世界で注目されるのはなぜ?自分を見つめることで執着をなくす。マインドフルネスの原点に迫る。シリーズ第14弾!
目次
第1章 なぜ今、禅?
第2章 自分をみつめるってどういうこと?
第3章 修行ってどんなことするの?
第4章 なぜ坐るの?
第5章 悟るってどういうこと?―自分の仏性に気づく
第6章 日常に禅はどう活かせるの?―社会とつながる「禅」
著者等紹介
石井清純[イシイキヨズミ]
1958年、東京生まれ。駒澤大学仏教学部卒業、同大学院博士後期課程満期退学。現在、駒澤大学仏教学部教授、禅研究所所長。2009~12年に駒澤大学学長、2000年にはスタンフォード大学客員研究員を務めた。専門は禅思想研究。禅学研究の国際交流も積極的に行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アルカリオン
7
著者は駒澤大学の学長も務めた禅僧▼著者ならではのエピソードは面白いのだが、純粋な著作ではなくインタビューを元に編集者が書いたもののようだ。「黄檗宗は臨済宗の一派」と言い切るなど、大雑把すぎて疑問の残る記載が散見される。インタビュアーとの会話の流れの中でわかりやすさ重視で行った説明をそのまま使ってしまっているのではないかと思える▼戦前は、臨済宗と曹洞宗の行き来は珍しいことではなく、臨済宗出身の僧侶が曹洞宗本山である永平寺のトップを務めた例もあるという話は興味深い。2020/05/30
元気伊勢子
5
判断力について悩んでいたところだったので、タイムリーな本だった。自己の探求と言うのは、死ぬまで続けることらしい。「見つかった❗️これでいい❗️」と言うのは、慢心に当たるそうで耳が痛かった。2022/07/10
ニコ
3
どこか足りない所がある、と思いながら全体を見ることが悟り。近づくのではなく、進み続けること。(なぜならゴールは無いから)進化とは変化し続けること、成果主義へのアンチテーゼに、なるほどなあと思った。“私に功徳を積ませて欲しい”2022/06/11
Hiroki Nishizumi
2
やさしく解説しようとしている。でも難解な公案を考えさせられた方が良かったんじゃないかなと感じた。2025/03/05
takao
2
ふむ2022/05/31
-
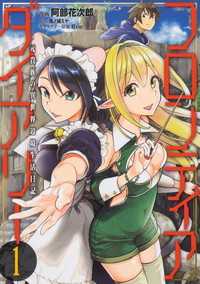
- 電子書籍
- フロンティアダイアリー ~元貴族の異世…
-

- DVD
- 君は僕をスキになる






