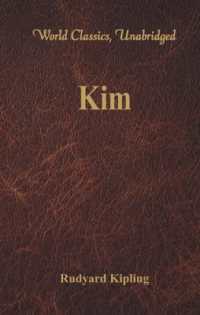内容説明
両親を失くし、お祖父さんと暮らす孤独な少女が、不思議の森で遭遇したカラスたちの教え「いのちの地動説」とは?新しい生命論で知られる科学者が、大震災後、鎮魂と、子供たちと日本の未来への祈りを込めて書き上げた哲学物語。
著者等紹介
清水博[シミズヒロシ]
1932年、愛知県生まれ。東京大学名誉教授、NPO法人「場の研究所」所長(理事長)、薬学博士。専門は、“いのち”の科学、生命関係学、“いのち”と場の哲学。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
エジー@中小企業診断士
5
東日本大震災を契機として書かれた「<いのち>の哲学物語」。著者は生きものが示す能動的な活き(はたらき)のことを<いのち>と名付けている。生きものの<いのち>が、それが生きている居場所と切っても切れない関係にあること、「生きている」ことと、「生きていく」こととは全く異なることである。死も「<いのち>の与贈循環」の一部である。これまでの科学技術や資本主義は「<いのち>の天動説」であり、これからの日本には持続可能性、文明の継続へ「コペルニクス的な転回」、つまり「<いのち>の地動説」という観点が必要であると説く。2025/08/10
マウンテンゴリラ
5
著者の生命哲学の理論を実践論として、子供にもわかりやすいような物語として提示したものと言えるだろう。我々のような頭の堅い大人が読むと、どうしても物語の奥にある深い意味を探ろうとし、それを論理的に掴むことで何となく事足れりとしてしまい勝ちであるようにも思う。しかしそのような論理的な理解のみでは、著者の意図が決して満たされない。それが、あえて子供向けの物語として展開した理由でもあるのではないだろうか。さて、われわれ大人達はこの物語を読んで、子供達に何を伝えることができるだろう。→(2)2017/12/31
Hazuki Hasegawa
3
お友達オススメの本ということで、読んだ哲学読本。とくに印象に残ったのは、文章中に何度も出て来る、「〈いのち〉の居場所」。私たち日本人が、今とても必要な考え方だと思います。2013/05/30
mattu
2
「いのち」に対しての価値観に共感。一気読みしました。 2つだけ「どうかな?」って、思うことが・・・ ①「いのち」を伝えるのに、震災を結びつけることが必要か?「震災」の言葉を使うことによって「いのち」が限定的なイメージなってしまう。そのため、哲学ではなく感じてしまう。 ②著者の「手紙」「あとがき」を読むことにより、「いのち」の物語に著者の価値観が押し付けられているように感じる。 ①②を除いても、「いのち」のも語りは考えさせられる話ですね。心に伝わるワードが多く物語には珍しく付箋を貼っちゃいました。2012/06/20
井上岳一
2
敬愛する生物学者の清水博先生が、震災後の日本のために書いた渾身の哲学物語。「いのちの与贈循環」とか「いのちの二重性」など、子どもどころか大人にも難しいコンセプトが鍵になっているので、読者は選びそう。でも読むべき本です。2012/03/19
-
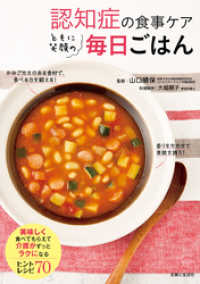
- 電子書籍
- 認知症の食事ケア ともに笑顔の毎日ごはん
-

- 和書
- エイプマン