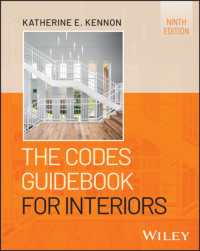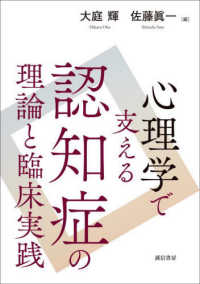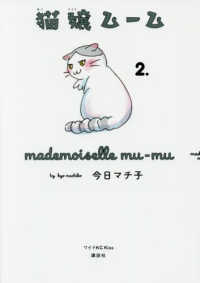出版社内容情報
19世紀後半から20世紀初頭の中国・清朝の洋務派を代表する張之洞が著した学問指南書。当時の科挙受験者の必携の書ともされ、現代中国においても評価が高い書物を翻訳。
内容説明
四川省から中国全土へと一気に広まり、「海内に流伝し、人は一編を手にするに幾し」と形容された、梁啓超・周作人・吉川幸次郎など中国を熟知する人々が絶賛する、中国古典を学ぶための必携書。
目次
行を語る 第一
学を語る 第二
文を語る 第三
学究語 第四
敬避字 第五
磨勘条例の摘要 第六
学田を置くよう勧める 第七
著者等紹介
深澤一幸[フカザワカズユキ]
1949年京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。元大阪大学大学院言語文化研究科教授。専攻、中国言語文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
電羊齋
13
張之洞が科挙受験生に向けた指南書。読書と学習の心得、経(儒教の経典)・史(歴史・地理)・子(思想・科学など)・集(文集・詩文など)など各分野での具体的な中国古典の学習法、具体的な科挙受験対策などが盛り沢山に紹介され、今でも参考になる指摘が多い。また付録の奏摺(上奏文の一種)には当時の四川省での替え玉受験など科挙での不正、それに対する張之洞の解決策などが書かれている。中国古典学習入門、具体的な科挙受験対策、清末の科挙制度の実態としてなどなど、いろいろな角度から読めて非常に面白かった。2025/06/20
さとうしん
12
清末の四川の学政であった張之洞が科挙の受験生に向けた訓戒。普段の行状や読書・学習の仕方などを語る。史書を読むのにダイジェストで満足してはいけないだとか、本は帰るなら買い、借りて葉いけないとか、耳の痛い言葉が多い。早期受験の戒めのようなものもある。細々としたことでは、『康熙字典』での別体の扱いなども参考になる。2025/05/11
つまみ食い
5
科挙受験者としての古典との向き合い方や避諱の詳細な解説など、今なら受験参考書といった形。科挙の受験者向けなので、「読書は必ず成果の有ることを期すべし (≒才能もないのに勉強をして徒に受験を繰り返し月日を費やすのならば、手に職をつけよ)」という節も出てくる。 基本的に論語・孟子などのテクスト中心だが、張之洞は洋務運動の中心だったこともあり、解説に出てくる「学堂歌」では西洋の科学や技術を学ぶ必要も詩にしている。2025/09/07
-

- 文具・雑貨・特選品
- 「十二国記」てぬぐい<紺>