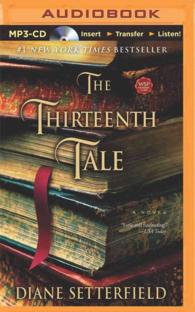内容説明
19世紀初頭、デリーの学者ミール・アンマンがペルシア語から翻訳したウルドゥー文学の白眉。1947年刊の蒲生礼一氏の流麗な訳に、現代までの研究の進展をふまえた解説を付す。四人の托鉢僧と一人の王が語る恋と冒険と大旅行を含む波瀾に満たち伝奇小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
106
お気に入りさんの感想を読んで、図書館で借りてきました。王様が4人の托鉢僧の話を聞くということなのですが、その話が奇譚が多く文化が異なればこのような話もあるのか、という類の話です。私は結構楽しめました。2018/09/17
syaori
46
「いかなる御仁も浮世の摩訶不思議な出来ごとに廻り逢われぬはあるまい」とは言うものの、四人の托鉢僧が王に語る彼らの旅の何と不思議で数奇なこと! 美しい御殿や庭園に魔神や魔法が飛び交い、木箱に入れられた瀕死の美女や鉄の檻に入れられて犬の食べ残しで飼われる男、地下の御殿で養育される皇子など次々と現れる謎と豪奢に目が眩むよう。また四人と王が邂逅したときに彼らの「宿望は必ずや達せられるであろう」という神秘の騎馬武者の予言も物語の推進力となっていて、大団円に向かって奔放に飛翔する物語に耽る楽しさを存分に味わいました。2018/08/17
roughfractus02
6
ムガル帝国期にペルシャ語とヒンディー語に共通の語彙や音韻構造を持ち、両言語の修辞を平易化したウルドゥー語で書かれた本書は、ペルシャの物語を作者が意訳したものだという。帝国末期の19世紀に出版された本書は、東インド会社の交易拡大と共にイギリス人が現地の言葉を学ぶ教科書として普及した。その痕跡か、子供のできない王に4人の托鉢層が語るその奔放な冒険・怪異譚は、西洋の言語習得者にも馴染みのある物語構造になっている。一方、托鉢僧が最後に余計な欲を出してさらに振り回され、その戒めを伝える点が本書の特色でもあるようだ。2022/09/15