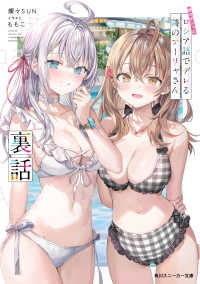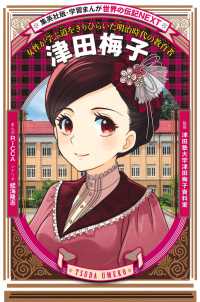出版社内容情報
中世の日本仏教界では、稚児をめぐって寺院間で戦いが起きるほど、男色文化が広がっていた。鎌倉新仏教が興った背景を、「戒」をめぐって描くスキャンダラスな仏教史。
内容説明
仏教には釈迦が説いた厳しい戒律がある。それにもかかわらず、日本の仏教界には、中世にはすでに男色文化ができあがっていた。稚児をめぐって争い、失っては悲しみにくれ、戒律護持を誓っては、何度も破る―。荒れはてた仏教界で、「戒律復興」の声とともに立ちあがったのが、鎌倉新仏教の宗祖たちだった。戒と僧侶の「身体論」から見た、苦悩と変革の仏教史。
目次
第1章 持戒をめざした古代(なぜ戒律が必要となったのか;待たれていた鑑真と国立戒壇;延暦寺戒壇の成立)
第2章 破戒と男色の中世(守れなかった戒―宗性の場合;僧侶の間に広がった男色)
第3章 破戒と持戒のはざまで(中世日本に興った“宗教改革”;女性と成仏;戒律の復興を人々に広める;延暦寺系の戒律復興と親鸞)
第4章 近世以後の戒律復興
著者等紹介
松尾剛次[マツオケンジ]
1954年長崎県生まれ。日本中世史、宗教社会学専攻。山形大学名誉教授。東京大学大学院博士課程を経て、山形大学人文学部教授、東京大学特任教授(2004年度)、日本仏教綜合研究学会会長を歴任。1994年に東京大学文学博士号を取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
64
仏教において戒は定・慧と共に三学の一つと数えられるほど重要なもの。本書は日本仏教がどのようにその戒に向き合ってきたのか、を主に中世の稚児、男色文化を例にとって解き明かそうとした一冊。主に鑑真来朝から明治に至るまでの戒を通して見た仏教史の趣があるが、中心となっているのはやはり中世。浄土教を中心として学んだ身としては、主に鎌倉新仏教は戒と向き合いそれを超越した所に到達したというイメージがあるけど、それと同時に戒を復興させようとした動きもあったのだなあ。今まであまり触れられなかった動きが興味深く読めました。2024/04/13
Jampoo
17
僧侶の同性愛について知りたくて読んだがそれだけでなく、戒律との関わりを軸とした日本仏教史をわかりやすく知れる。 朝廷権力と結びついて行われた授戒が、その世俗性と相まって形骸化し、そのアンチテーゼとして国家権力の枠組みから抜けた遁世僧が出てくる。 しかし戒律復興を目指した真言律宗の僧は、戒律で禁じられていた土木行為や、死穢に触れる葬送を積極的に行ったようだ。 日頃から戒律を厳しく守る生活をする事で、人々を救う為の破戒を正当化したというのが興味深い。2025/12/27
眉毛ごもら
5
破戒が結構早い段階から進んでいたが自分の意志で出家したならともかく家において置けないから出家してねというパターンが多くなるとそりゃ堕落するわという気持ちも。かの有名な百人以上は稚児と致しませんの僧は飲酒の誓いも失敗していたらしい。笠置寺では清らかにいますという宣言により南都の有名寺院の状態はお察しであると。酒を売るのを唆すのもアウトなのに京中の酒屋と山門の関係は?と思ったら上納金で免罪とか免罪符みたいなことやってる。乱痴気具合は知ってたから特にだが他の仏教国からの目が厳しいらしいと聞いてそこは耳が痛いな。2024/04/29
Fumoh
3
著者の説明がとても分かりやすく、楽しく読んだ。中世の仏教徒の世界がよく分かった。「破戒」というと、シンプルに考えたら異端者のように思えるが、ルールを正しく守るほうが異端だったとは、なるほどと思わされる。信長の比叡山焼き討ちや、傭兵の根来衆などを知っていたので、中世の仏教徒がどういう存在だったか、なんとなくは察していたが、幅広い文献から分かりやすく説明をしてくれて、納得がいった。早い時期から「国家公務員」として地位を与えられた官僧たちは半世俗的権力を担っていたわけで、貴族の子息なども幼少から仏門に入れられて2023/11/28
mongkeke_tarikh
2
平凡社新書版を読んで久しかったが、この度平凡社ライブラリー版かつ増補版として出たと聞いて購入した。のだけど、どうも折角単行本で贖ったにも関わらず、読む機会を逃してばかりいたので、電子版を買い足せばぼちぼち読めるのではと思い、先般そちらも購入していた。それで同じ著者の松尾氏の先著である忍性の方を先に読み進めていたのだけど、こちらもどういう訳か読みたい時に手元にない状況が何度か続いて通読が断続的になってしまい、もうこちらを先に読んでしまおうと改めて通読する事にした次第だった。2025/12/09
-
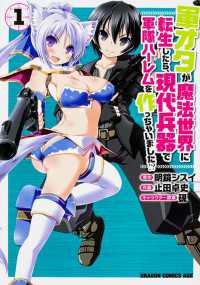
- 電子書籍
- 軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器…