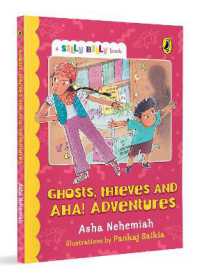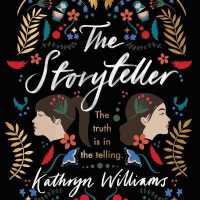内容説明
池波正太郎の酒と食の道楽は、小学校時代にまでさかのぼる。本書はその道楽作法を、作家のエッセイに学びとり、包丁さばきを盗み、さらにその江戸・東京の味を相伴しようという虎の巻。四季折々の味が愉しめ、即席食通、にわか料理自慢になれる、本邦初の酒食料理帖の巻二。
目次
第1部 明治・大正・昭和の味(料理忘れもの;江戸前の酒肴二品―葱と鶏皮の吸物、合鴨と葱の炒りつけ;鰻の食い方―蒲焼、鰻ざく ほか)
第2部 むかしのホテルの味、レストランの味(料理忘れもの;トロワグロの料理―兎のソテー;プチホテルの朝食―ジャムとフランスパン ほか)
第3部 食道がうなる味(料理忘れもの;鮨と天ぷら談義―名人秘伝の料理法;味自慢談義―イカブツ、サンドイッチ=男の料理法 ほか)
著者等紹介
池波正太郎[イケナミショウタロウ]
1923年、東京・浅草生まれ。下谷西町小学校を卒業後、兜町の株式仲買店に勤める。戦後、東京都の保健所の職員として勤務するなかで、読売新聞社の演劇文化賞に戯曲作品を応募、46年『雪晴れ』で入選する。その後、作家・長谷川伸の門下になり、新国劇の脚本・演出を担当する。長谷川伸のすすめで小説も手掛けるようになる。1960(昭和30)年『錯乱』で直木賞、77年『鬼平犯科帳』その他により吉川英治文学賞、88年に菊池寛賞をそれぞれ受賞する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
- Women's Suffrage in…