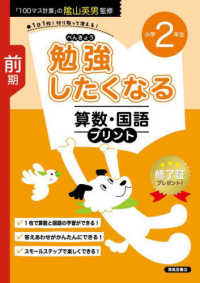内容説明
池波正太郎の酒と食の道楽は、小学校時代にまでさかのぼる。本書はその道楽作法を、師のエッセイに学びとり、包丁さばきを盗み、さらにその江戸・東京の味を相伴しようという虎の巻。四季折々の味が愉しめ、即席食通、にわか料理自慢になれる、本邦初の酒食料理帖の巻一。
目次
1章 春のそうざい(白魚の椀盛り(夕・酒肴)
蛤の湯豆腐(夕・酒肴) ほか)
2章 夏のそうざい(初鰹二種―鰹の刺身・生鰹節の甘酢和え(夕・酒肴)
焼太打ち冷やむぎ(夜食) ほか)
3章 秋のそうざい(秋鯖のレモン〆(酒肴)
豚肉のうどんすき(夕) ほか)
4章 冬のそうざい(浅蜊と白菜の小鍋だて(夕・酒肴)
鮪のヅケ焼き(朝・夜食) ほか)
著者等紹介
池波正太郎[イケナミショウタロウ]
1923年、東京・浅草生まれ。下谷西町小学校を卒業後、兜町の株式仲買店に勤める。戦後、東京都の保健所の職員として勤務するなかで、読売新聞社の演劇文化賞に戯曲作品を応募、46年『雪晴れ』で入選する。その後、作家・長谷川伸の門下になり、新国劇の脚本・演出を担当する。長谷川伸のすすめで小説も手掛けるようになる。1960(昭和30)年『錯乱』で直木賞、77年『鬼平犯科帳』その他により吉川英治文学賞、88年に菊池寛賞をそれぞれ受賞する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
めしいらず
60
著者が著してきたエッセイや日記から、食に関するものを抜粋した本。ここに登場する惣菜は、どれもこれも極めて簡素で、本当に美味しそうなものばかり。だからこそ真似っこして作ってみたくなること必至。旬の素材に四季の移ろいを感じながら食することの幸福は、この国に生まれた者にとって何事にも代えがたいもの。何より一食たりとも無駄にせず、徹底的に味わい尽くすその心意気。本当の贅沢とは何なのかを、私たちに教え諭してくれるよう。素敵な生き様に憧れてしまう。そして著者が感じるノスタルジアは、この本の絶妙な調味料だった。2016/07/22
うめ
27
食材に敬意を払う。これに尽きるんだな。食べ方、調理法もシンプルなものばかり、そして無駄がない。まさに家庭料理。お惣菜。高価で華やかではないのだけれととても美味しそう。食材と相談しながら自炊するって、贅沢なことなんだな。2014/12/27
としちゃん
24
池波正太郎先生の食日記、食エッセイからおいしそうな部分を抜粋し、イラスト入りで解説した本。2003年に出版された時は単独の読み物だったのに、2011年に文庫になった時、巻一、二になっていたのを最近知り、せっかくなので巻一から再読。どの料理も特別な何かがあるわけではないのに、読んでいるうちに無性に食べたくなり、口の中も頭の中も妄想で一杯になり、気がつけば台所に立って作り始めてしまう。書かれてから随分時間がたっているのに、その料理の香りも温度も、全く変わらず、むしろますます香り立つ。恐るべし。2016/05/30
Shin
12
池波先生の小説・随筆を読んでいて、ひとつだけ難儀するのは腹がへること。そして食べること、飲むことを心から愉しむ姿に、人生の達人としての尊崇の念を抱く。そんな池波食三昧のエッセンスを取り出した随筆集+簡単なレシピ集。取り上げられた料理はすこぶるシンプルで、真似をしようと思えばすぐできるものばかりだけど、本当の意味での〈味わい〉を再現するためには、レシピを真似るだけでなく自分自身の人生の深みも増して行かなければならないだろう。食は人生であり、ゆえに三昧の境地への道は遠い。2013/10/06
ikedama99
11
職場の図書館から。なんでこんなしぶいのが・・・と思いつつ、でも面白いというか食べたくなるというか、食べたいと作ってみたい料理が多々あった。身近な料理・・ソースカツレツや小鍋などや昔の弁当を思い出させてくれるような話なども多く、楽しく読めた。特に小鍋料理・・小さな土鍋で一人前を作って・・というのはやってみたい。このような料理が出るかもしれない小説はまだ一つも読んでいないことに気が付いた。何か一つ読んでみようか。2020/12/05
-

- 洋書
- A Lost Hero