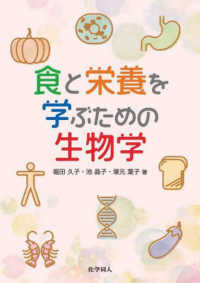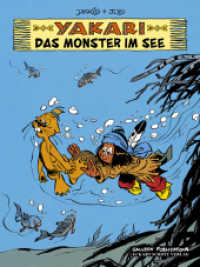内容説明
米俵を積んだ馬、橋と中島、松の根元の石…上杉本『洛中洛外図』に描かれた小さな一齣から読者はいつのまにか中世京都の街頭につれ出される。米座と関、伊勢信仰と病、降格させられる神…史料の細部を読み抜く目が、洛中洛外の時代における都市の鮮烈な眺望をひらく。上杉本成立をめぐる卓論「公方の構想」を含み、音や匂い、手触りにいたるまで中世都市の具体を探りあてようとする名著の増補版。
目次
1 上杉本『洛中洛外図』から(馬二題―上杉本『洛中洛外図』の一齣;失われた五条橋中島;弁慶石の入洛;公方の構想―上杉本『洛中洛外図』の政治秩序;ウラにそそぐ眼―町田本『洛中洛外図』の都市観)
2 洛中洛外の時代(荘園解体期の京の流通;伊勢の神をめぐる病と信仰;飢饉と京菓子―失われた創業伝説;禁庭の砂;中世の祇園御霊会―大政所御旅所と馬上役制;五条天神と祗園社―『義経記』成立の頃;下人の社寺参詣―抜参りの源流;一青年貴族の異常死―父・山科言国の日記から)
著者等紹介
瀬田勝哉[セタカツヤ]
1942年、大阪生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。現在、武蔵大学教授。専攻、日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
58
洛中洛外図屏風に描かれた中世の京都。そこに描かれた馬や橋、石といったものに注目し、そこから当時の情景や生活を生き生きと蘇らせた一冊。鴨川に当時中州があった事や面白い名だなと思っていた弁慶石町の謂れ等が紐解かれていて夢中になって読む。当時と現在が変化しているにも関わらず地続きである事を思い知らされた。後半は伊勢信仰や青年の横死といった事件を題材に、当時の人々の心性に迫っている。青年の事件については日記が淡々としている分が余計に胸を打つ。あと京菓子を題材にした一編、よくお土産に買うので特に印象深いなあ。2024/06/06
田中峰和
8
現在の松原通が中世の五条橋だったことは有名だが、この辺りは川幅が広く中島に向け二つの橋があったことは屛風図からもわかる。不思議なのは当時の文献で、二つに分かれた橋の説明が見当たらないのが不思議だ。中島には法城寺という寺があり清明塚があった。安倍晴明が氾濫する鴨川の水害を防いだことが由来らしい。上杉本の作者は狩野永徳だが、町田本は祖父の元信の作品。町田本が井戸や厠など裏の空間も描いたのに比べ、上杉本は、表の活況に徹している。また公方と禁裏、幕府の要人など屋敷を区別して描いた上杉本には政治の影響がみられる。2020/03/10
アメヲトコ
6
単行本94年刊、平凡社ライブラリーに増補して09年復刊。洛中洛外図上杉本の今谷説を批判した「公方の構想」をはじめ、中世京都の都市社会の実像を浮き彫りにする論集。ところどころ力技と思う箇所もありますが、着眼点が鋭く、「飢饉と京菓子」「下人の社寺参詣」などは短くも名文です。2021/10/31
陽香
2
200901092016/07/11
mallio
1
論文をもとに纏めた本だと思いますが、なんというか、論文を読んでいるというよりは、推理小説の謎解きを読んでいるような・・・ え?次はどうなるの?とワクワクしながらページをめくっていき、最後まで読み終えると、室町時代の洛中洛外の様子、当時の人が大切にしていた考え方、生き方、商業のあり方、などについて自然と理解が深まってるという・・・ いい意味で騙されたような名著です。2020/09/21