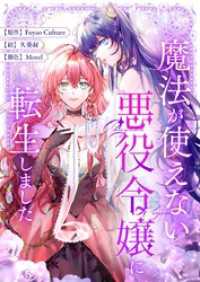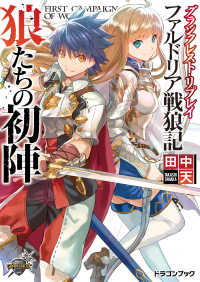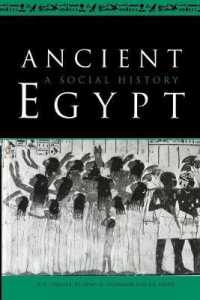内容説明
十九世紀半ば、機関銃の登場により、過剰殺戮と呼べる概念が戦争に導入された。戦争の主役は、もはや人間ではなく、機関銃であることが明らかになった。第一次世界大戦では、死者の八十パーセントが、機関銃の犠牲者となった。近代の軍事技術の革新によって、人間の社会はどのように変わっていったか。背筋が寒くなる人間と機関銃の歴史。
目次
第1章 新たな殺戮法
第2章 産業化された戦争
第3章 士官と紳士
第4章 植民地の拡大
第5章 悪夢―一九一四~一六
第6章 時代の象徴
第7章 新しい戦争の流儀
著者等紹介
越智道雄[オチミチオ]
1936年愛媛県に生まれる。広島大学大学院博士課程修了。明治大学商学部教授を経て、明治大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
67
アメリカ南北戦争から第1次世界大戦までの機関銃という「新兵器」が欧米社会でどう扱われ、認識されたかを丹念にまとめている。この時代ヨーロッパでは依然として「騎士道精神」的軍事信仰が残っていたため、機関銃という途方もない殺戮機械の出現に対しても、軍上層部は正しい認識を持たず、それが多くの兵士の犠牲を生んだことを明らかにする。さらにアフリカなど「有色人種」相手にはそうした価値観はなく、ためらわず使用したとのこと。本書は機関銃と個人兵器であるサブマシンガンを区別せず扱い、1920年代のギャングにまで話が及ぶ。2025/01/13
モリータ
11
◆原著は1975年刊、1986年新版。訳単行本は1993年刊、本書は2008年刊。著者のプロフィールが書いてなく、ネットでちょっと調べても出てこないので断念(疲れてるし)。◆小6の時の旅行で函館・五稜郭で観た再現ビデオに手回し式ガトリング砲(武田観柳がぶっ放してるやつね)が出てきて、それより前に観ていた『二百三高地』でロシア軍が機関銃で日本兵を薙ぎ倒していたのを思い出し、明治初期に機関銃を輸入してたのになぜ陸軍に導入されてないんだ!と思ったのは積年の疑問だった。2020/08/23
左手爆弾
8
本としては、繰り返しが多く、時系列が不明瞭なところがあり、内容に不足があると感じたところも多い。しかし、問題の発見と整理の仕方は実に見事で、他の様々な研究領域にも応用できそうだ。全体としては、機関銃が技術的に作りだされることと、それが実際に重要な戦場に投入される際の「イデオロギー的要因」に特に重点を置いている。人間は技術的に有用だからそれを用いるのではない。自分の描いている世界観にそぐわないものは、使わざるをえない場面に追い込まれるまで使わない、ということか。2019/04/21
in medio tutissimus ibis.
8
本書は兵器の受容についての書であると同時に、死の受容についての書でもある。就中、瞬間的な大量虐殺の受容の難しさは、その圧倒的な現実を考えれば些か奇妙に映る。西部戦線の塹壕から突撃を繰り返す貴族出身の士官たちも、呪術により銃弾を水に変えられると信じるアフリカ人や太平天国も、その点では変わらない。同胞の死骸の山を前に、それでも自分の無常を覆い隠す無明の源と、それを照らす灯の在処や何処。遠隔地での他民族の虐殺についての無感覚など、この奇妙さに比べれば正常の範囲だろう(この時代の資本家による労働者の収奪を見よ)。2017/11/10
中島直人
7
機関銃を基にした、技術視点からの社会史といった側面強し。多くのエピソードがちりばめられ、読みやすく面白い。2014/11/28