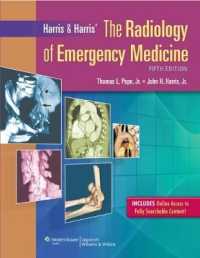内容説明
響き、音、そして音楽。ひとはそこに何を見出し、求め、愛してきたのか。本書は、音律という「音の基準」をフォーカスに、古代のギリシアや中国、アラブ、西欧における多様な音律の歴史を縦横に探索し、平均律という近代の欲望から自由な、これからの音楽の可能性へと誘う注目の書。
目次
第1章 古代ギリシャの音律(比率による音の思考;純正音程の操作 ほか)
第2章 古代中国の音律(黄帝伝説―音律の始まり;西方とは ほか)
第3章 アラブの音律(音律と楽器;ウードとアラブの音律 ほか)
第4章 西欧の音律(モノコードによる宇宙;グレゴリオ聖歌の音律 ほか)
第5章 現代の音律(平均律を超えて;ハリー・パーチの音律 ほか)
第6章 音律のあらたな実践(音律にめざめる;耳の訓練―コンピュータによる即興演奏 ほか)
著者等紹介
藤枝守[フジエダマモル]
1955年、広島市生まれ。作曲家。カリフォルニア大学サンディエゴ校音楽学部博士課程修了。博士号(Ph.D.in Music)を取得。作曲を湯浅譲二、モートン・フェルドマンらに師事。ハリー・パーチ、ルー・ハリソンに影響されながら、純正調によるあらたな音律の方向を模索。近年は、植物の電位変化のデータに基づく『植物文様』という作曲シリーズを展開。また、箏や笙などを中心とした音律の可能性を追求する合奏団「モノフォニー・コンソート」を組織。九州大学大学院芸術工学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bartleby
へくとぱすかる
bittersweet symphony
あがた
サニジョプッ