内容説明
明治三十九年、著者は平取にてユーカラと出会う。―変幻怪奇な無限の曲を分化していて、その長いものは、冬の夜長、ほだ火を囲んで、寝るを忘れ、一夜をうたい明かして、夜のしらじらと明けるころ、やっと一曲終る。これが、金田一アイヌ学の始まりだった。樺太、北海道で、ユーカラの世界の人びととの心暖まる交流を描く、感動の随筆集。
目次
片言をいうまで
アイヌの話―「心の小道」余話
安之助
樺太便り
思い出の樺太
イランカラプテ―アイヌをにっこりさせる一言
太古の国の遍路から
盲詩人
人差し指の話
ペンを休めて〔ほか〕
著者等紹介
金田一京助[キンダイチキョウスケ]
1882年、岩手県生まれ。言語学者。国学院大学教授、東京大学教授を歴任。盛岡中学時代には短歌を詠み、与謝野鉄幹主宰の『明星』の同人となる。石川啄木とは高等小学校以来、啄木が亡くなるまで親交があった。東京大学の学生時代にアイヌ語に関心を持ち、その研究は、アイヌ語、アイヌ文学、アイヌ文化全般にわたって生涯続けられた。とくに、アイヌ叙事詩ユーカラの筆録とその研究に新分野を開拓し、『アイヌ叙事詩ユーカラの研究』全2巻(東洋文庫論叢)で学士院恩賜賞を受賞した。一方で、国語辞典や教科書の編者としても知られ、現代仮名遣いについての提言も行った。1971年没
藤本英夫[フジモトヒデオ]
1927年、北海道生まれ。北海道大学卒業。元北海道埋蔵文化センター理事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
47
著者はかつて三省堂の国語辞典(旧・明解)や中学教科書でお馴染みだった(私はカネダハジメ京大助教授だとずっと思っていたが)。戦後の国語審議会を先導した言語学者だが、アイヌ文学の研究の開拓者としても知られる。本書は、著者初期のアイヌ関連のエッセイ集。学生の頃、明治39年から北海道や樺太のアイヌ人を訪ねアイヌ語を学びながら、叙事詩ユーカラを発見する。ユーカラを何夜にもわたって吟じる古老をアイヌのホメロスと讃え、若い娘が次から次へとユーカラを口誦するのに稗田阿礼を実感する。アイヌ文化を発見した驚きがみずみずしい。2015/05/05
やまはるか
18
金田一京助のアイヌ研究に関連する随筆集。ユーカラは文字を持たないアイヌが口承する叙事詩。金田一は記録として残すため北海道やカラフトにアイヌの古老を度々尋ねる。そうした中で後に「アイヌ神童集」を編纂する知里幸恵を見出し、知里が金田一宅で亡くなるまでの様子を細かに記している。アイヌがどのようにして土地を奪われて行ったか、戦ったアイヌの人々の話として描いている。脅され騙され、追い立てられて取り込まれて行く先住民族共通の歴史がある。「アイヌ神童集」今なら違った味わいが期待できる気がする。2024/12/22
紙魚ったれ
2
感心しながら読んでいくと最後に金田一京助その人に対する批判があるという一文を見て「およ」と軽く調べると、まぁ色々ありまして、やっぱり完璧な人間なんぞはおらんものだし、どうあっても人間臭さというのは誰によらず身を離れがたくつきまとうもんだとしみじみ思った。 それはそれとして、本著でもってアイヌへの関心は高まる一方であったし、読みやすい文章でよかった。2019/01/03
雨彦
2
金田一京助がこんにち批判を受けることもあるのは、やはりアイヌ学の創始者として不可避なのだろう。ただ、こうした随筆を読むと、ただひとすじに学問に身を捧げたばかりではなく、かかわったアイヌを単に研究対象と見るのではなしに、心の交流をもはかっていたと感じられるのだが……。2013/07/04
kaizen@名古屋de朝活読書会
2
樺太アイヌ語の収集の苦労が最初に書かれている。 絵をかいて、それをなんと呼ぶかを聞くのがよいという方法が大事であることがわかった。 警戒する大人に比べて、くったくのない子供を攻めるのがよいこともわかった。 子供は絵に興味があるので、絵をかけば集まってくることもわかった。 北海道では目はシクであり、樺太ではシシというとのこと。 アイヌ語調査の苦労が分かった。2012/05/01
-
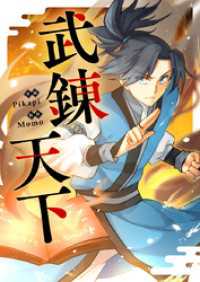
- 電子書籍
- 武錬天下【タテヨミ】第309話 pic…
-
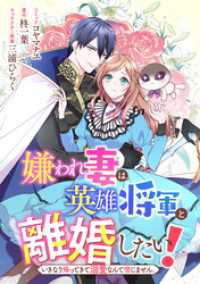
- 電子書籍
- 嫌われ妻は、英雄将軍と離婚したい! い…
-
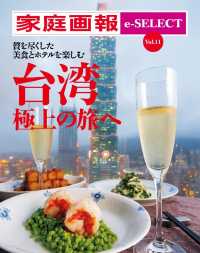
- 電子書籍
- 家庭画報 e-SELECT - Vol…
-
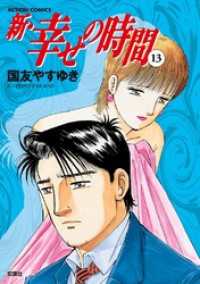
- 電子書籍
- 新・幸せの時間 13巻
-

- 和書
- 下田情死行




