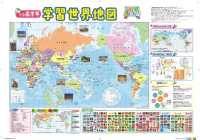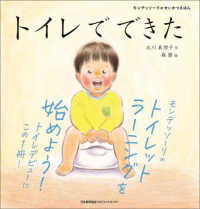内容説明
世界で唯一元号を採用し、婚姻の相性や暦の本による日常行事の吉凶など、長い歴史のなかで、日本的伝統としてわれわれの日常生活に融け込んできた陰陽道。為政者たちはこれをいかに利用してきたのか。われわれはこれをいかに縁としてきたのか。陰陽道の発生から現代に至る残影までを、平易に、刻明に説いた通史入門の決定版。
目次
第1章 陰陽道の起源と日本への伝来
第2章 祥瑞と災異
第3章 神仙と冥府
第4章 王朝貴族と陰陽道の名人たち
第5章 易に心酔した政治家
第6章 栄枯盛衰の世と予兆思想
第7章 山伏と陰陽道
第8章 密教と陰陽道
第9章 鎌倉武士と陰陽道
第10章 宮廷陰陽道の没落と民間陰陽道の発展
著者等紹介
村山修一[ムラヤマシュウイチ]
1914年、大阪府生まれ。文学博士。京都大学文学部史学科卒業。京都女子短期大学、大阪女子大学、愛知学院大学などの教授をつとめた
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
5
購入日は2001年。陰陽道について歴史的経緯を知るために読んだ。陰陽道は本来が式神を使った呪術ではなく、易を背景とした哲学であり、技術であった。『易経』は基本テキストだが、「陰陽師もの」で取り扱われることはまずない。平安時代には占いや呪いばかりがもてはやされる一方で、一部の人が易に深入りした。内容は多岐に渡るため、要約も大変な上に大分内容を忘れているので、再読したい。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
4
2001年刊。 第一章:陰陽道の起源と日本への伝来。もちろん起源は中国。陰陽道には二つの側面があり、宗教的哲学的な面と技術的な面がある。前者は陰陽二元論と五行説とを組み合わせた「陰陽五行説」で、後者は天体の観測暦の作成となる。夏王朝では陰陽道を連山と称し、次の殷王朝では帰蔵と呼び、どちらも現在に伝わっていない。更に次の周王朝で易が出来て『易経』として現在まで伝わっている。本書にも「女帝=シャーマン」…脱魂と神がかりがシャーマンの条件ですよ、と。→2024/04/27
眉毛ごもら
3
陰陽道についての話を飛鳥時代から江戸時代まで集めた本。講演の活字化らしく丁寧な文体で書かれているので読みやすい。陰陽道が中国から入ってきたあと神道や仏教、道教などとごちゃまぜになる様子。段々と忌み日や儀式が増えてきたりパフォーマンスが派手になったりして公のものから庶民のもとまで広がるのもよい。有名所の安倍晴明やその一族の逸話ももちろん載っている。驚いたのが鎌倉幕府が陰陽道に傾倒しててかなりの数の儀式を行っていたことである。色々血生臭かったから験担ぎ及び怨霊鎮めに躍起になってたのかなと思うとなかなか業が深い2022/04/23
愛奈 穂佳(あいだ ほのか)
1
【大学在学中の4年間で、卒業後に進みたい業界に関係ある本を1000冊読みなさい、と言われたので挑戦した記録】 #6341997/09/30
そーだ
1
読んでいて面白く、良い本だとは思うけど、資料の引用はちゃんと考証してあるのか不安に思った。また、索引がちゃんと機能していないこともあり、学術的にはあまり役に立たないかもしれない。初出は朝日カルチャーブックス版(大阪書籍・1987年)。2012/07/08
-

- 電子書籍
- 最強ご主人様に愛され尽くす独占婚【タテ…