出版社内容情報
1807年刊行のヘーゲルの主著。意識が感覚という最も低い段階から経験を経て自己意識に、さらに理性から《絶対知》に到達する過程を描く大著の下巻。定評ある翻訳の改訳補訂版。
内容説明
現代哲学の源流と言われるヘーゲルによる哲学史上最もすぐれた作品の一つ。人間の意識の展開が、同時に人類の歴史というかたちで叙述される。意識、自己意識、理性、精神、宗教、絶対知という過程を辿る思索と洞察の書。
目次
D 精神(精神;宗教;絶対知)
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
11
部分的には分からないところだらけだったが、最後まで読んでみて、流れというか、全体的な話は少し読み取れた。そしていわゆる「弁証法」も読みつつ体験した。「最も低い単純な意識から、最も高い複雑な意識に至るまでの、全意識の展開を説いたもの」(解説p.424)という読み方が私にはできた。それと同時に、私という個人から出発して、普遍に至り、それは人類の歴史として我々の後に残る、というこの過程を示しているようにも思われた。そして根本には、主観と実体との交通はいかにして可能か?という問いに答える試みであったともいえよう。2023/10/16
記憶喪失した男
7
物自体という単語は一度も出てこない。非常に難解な書物である。文体は面白い。2016/09/10
グスタフ
4
ヘーゲルを「頭でっかち」と批判したのは、マルクスだ。難解な、ヘーゲルの思索の跡を必死に追いかけながら、その言葉に共感していた。マルクスが、精神ではなくて、生産力が歴史を変革し社会制度を作り出す原動力だと、そっくりその主張をひっくり返そうとしたのがよくわかる。また、ヘーゲルの信仰、教養、道徳のもつ欺瞞性へのさりげない指摘は、実は容赦なく厳しい。2011/11/27
CCC
3
確かなものについて本気で書こうとするとこうなるんだろうなと感じる。2015/01/17
hitotoseno
3
長谷川訳で読んでいるが覚え書きとページ稼ぎのためにここを利用。理論的な裏付けが主立っていた上巻に対し、下巻では抽出された認識に基づいて実践的な面を分析していくという段取りになっている。そのため見通しもよく、理性的なもの⇔現実的なものというヘーゲルの主張を裏付けられる様がよくわかる……しかし、これはヘーゲル自身序文で唾棄したはずの形式主義のやり口と相似してはいないだろうか?(一応反論も成り立つ気はするが……)特に宗教の章となるとそうしたきらいが甚だしい。理論を実践で裏付ける、これは科学の手法なら構わない。2012/02/03
-
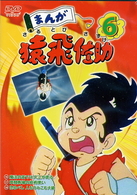
- DVD
- まんが猿飛佐助6






