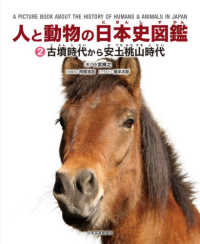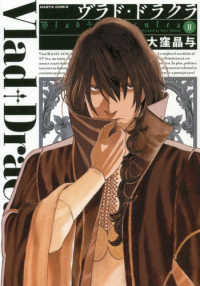出版社内容情報
ヘーゲルの主著(1807年刊行)の原文の構造に沿って完訳。意識が感覚という最も低い段階から経験を経て自己意識に、さらに理性から《絶対知》に到達する過程を描く大著の上巻。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
11
初めてヘーゲルの大著を読み通した。『エンチュクロペディー』はかじったことあったけど。上下巻あるので、ここでは動機と全体的な感想を残す。「サルトルを充分に理解するには、ヘーゲル、フッサール、ハイデガーを理解せねばならない」という見解を耳にしたことがある。それで、ヘーゲルはからっきしであったからこれを読んだ。(自分の先生は、『エンチュクロペディー』を推していたけども。)正直ドイツ観念論はカント止まりであったし、さすがに色々と知らないことが多すぎたように思う。難解な書物だった。2023/10/16
記憶喪失した男
8
物自体についてはほとんど語られないので、カントの弟子という認識はまちがっているとわたしは思う。極めて難解である。しかし、わたしはヘーゲルの述べる哲学が自分のいる世界の存在の構造だとは思わない。2016/09/09
Z
7
ている。ここで、個々の性質に着目すると、白は黒、赤など他の色とは共存せず対立する関係にある。物態は性質の雑多な集積ではなく類的性質のどれか一つを許す個別的な「一」なるポジションでもある。物は普遍的な時空のなかで、一般的な諸性質群が、一というポジションを共有するものである。(論証的とはいいがたいがとにかくこれを議論の叩き台に据え以降の論が展開する)2意識の物の経験。意識は何か一つの物を見る。そこには多様な性質が表現されている。性質は他の対象にも妥当するものだから、物は一般的なものである。さらにある性質は同じ2021/04/22
Z
6
白さは規定されず、他の特徴、赤や黒などと比較されて規定される。このとき対象は単なる特徴の集まりでなく様々な類的特徴のうちどれか一つのみ場所を占めることができる排他的なポジションでもある。ここに特徴に空間的な規定が与えられ、延長と特徴の結合として物の概念は完成する。②知覚が物に対する無反省な態度。まず知覚は物と性質の分離を知らない。知覚されるのは性質であり物そのものとは何かを考えるとそれはカントのように物自体という他ないだろう。ひとまずヘーゲルは知覚が対象から物自体という概念を取り出す過程を描く。まず対象は2021/06/28
Z
6
=感覚的私念は、無媒介と前提され、感覚的個別性同士=このもの、この私の接触を絶対化するものである。思い込まれた「これ」は 、点のようなものでなく広がり(複数のこれの集合)をもちつつ、そうでないこれを排除する。媒介、否定、一般性を経ないと思い込まれた個別性へ至ることはできない。ここで思い込まれた感覚的個別性から一般性と対立した知覚的個別性を吟味しなくてはいけない。「知覚」①冒頭は物の難解な定義。意識は移ろうが対象は動かない。よって真理の基準は対象たるべきだ。感覚的対象は「これ」としかなかったが知覚は自己2021/06/27
-

- 電子書籍
- 親バカ暴君の溺愛日記【タテヨミ】第43…