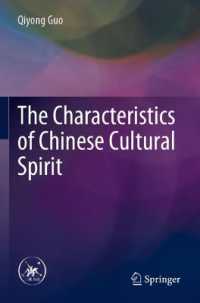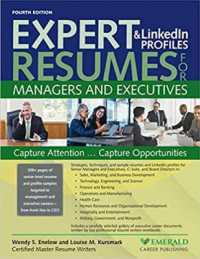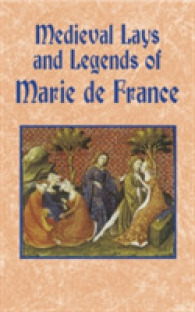内容説明
『ペッパー警部』とわらべうたはそっくり?!西洋音楽文化と日本的音感のはざまでダイナミックに変化する戦後歌謡曲。なつかしのヒットソングを徹底解剖。
目次
1 歌謡曲の基層(歌謡曲の源流をさぐる;森進一はなぜうける;『ペッパー警部』と平安音階)
2 歌謡曲の音楽構造(歌謡曲の音楽構造;異種交配の音楽性;ヒット曲の解剖 沢田研二の場合;演歌のディナーミック)
補稿 現代日本の歌謡風土
補稿 歌謡曲の音楽性
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
MASA123
8
本書は1984年に書かれた本なので、対象は、昭和歌謡曲であり、ユーミンや井上陽水は含まれない。戦後の歌謡曲は、ヨナ抜き5音階の短調が主流で、日本古来の、わらべ歌、民謡、などにルーツがあるそうだ。ピンクレディー「UFO」はわらべ歌。筆者が新タイプとしてあげている曲がある。西洋音階の長調「君のひとみは10000ボルト」、ヘミオラ(ポリリズムの一種)の「雨(小柳ルミ子)」、アウフタクトの「ダーリング(沢田研二)」等々・・著者は1983年没なので、歌謡曲がジャンルを超えて、jpopに進化する予言のようでもある。2022/04/02
OjohmbonX
5
戦後~70年代の歌謡曲の、主に旋律の音階に関する概説。西洋の7音階と伝統音楽がぶつかった結果、5音階の47抜き長・短調や26抜き短調が生じて、和声重視の西洋音楽からは退屈で貧しく見えるけど、その音の間の広さを利用して揺れたりズラしたりして豊かにしてるという。わらべ歌や謡曲に似た構造だけどハーモニーもつけるために西洋との折衷構造になってる、どの音階がヒットするかに波がある、そんな話が具体的な曲の譜面も見ながら指摘され、各年の流行曲と音階の対応表までついてる。元は80年代初めの本なのでその後の推移も知りたい。2015/02/21
BsBs
2
日本の歌謡曲を、主に音階から、サブではコードや強弱などの側面から多角的に分析。70年代までの歌謡曲の構造を追える。 氏の大作である『日本伝統音楽の研究』では歌謡曲が全く対象に入っていないことが問題だったが、その指摘に対するアンサーソングとなっている。 ラドレミソのペンタトニックについて佐藤良明氏はブラックミュージック由来だと語っていたが、それをわらべうたの音階であると真っ向から挑戦を仕掛けていて面白い(構図としては逆だが)。様々な音楽を日本風に再解釈した結果、わらべうたに回帰した…といったところか。2025/05/25