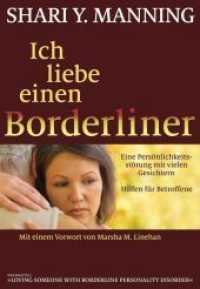感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みのくま
9
本書はうまくいった類の対談ではない。特に網野氏の方が阿部氏の問いかけにうまく返答できていないように感じた。しかし「社会史」の話題で腑に落ちた事がある。両氏は既存の歴史学に反旗を翻しているわけだが、だからと言って軽薄なトレンドに乗るわけではない。両氏は孤独な闘いを強いられているという共通点があったのだ。それは両氏の著作にも表れており、いわば実存が投影されている。だからこそ両氏の著作は面白いのだ。本書自体はいい本とは言い難い。だが両氏の魅力の断片を見つける事はできる。本書の次は両氏の重厚な著作に挑まなくては。2022/01/07
てれまこし
6
今日切り売りされる「リベラル・アーツ」とか「教養」というのは、ヨーロッパ特有の「公」と関係がある。「酔っぱらえない宴会」の延長線上に宮廷やサロンでの社交が生じて、ウィットの利いた会話、教養に裏打ちされたユーモア、優雅ないでたちや立ち振る舞いというものが培われる。エリートと大衆の境目はここ。ヨーロッパの外ではこうした「社交」がないから、エリートでも無教養で「下品」に見える。「男らしく」酔っぱらうのが普通なんである。だが、特殊なのはどうもヨーロッパの方で、日本の酔っぱらいおじさんの方が人類普遍に近いらしい。2019/12/05
(ま)
3
日本中世史家と西欧中世史家の割とルースな対談 宴会・贈与・公・・・無縁とかアジールに直ぐ結びついちゃうし...2023/06/29
凡栽
3
西洋中世史学者と日本中世史学者の対談。東西の中世の共通点、また相違点などについて書かれている。当時の人類が如何なる暮らしをしていたかを知る為には「民俗学」や「歴史学」などといった区切りは意味がないという提言。2011/07/19
絜
2
はじめて歴史家の対談を読んだ。時事的性格が濃いはずの対談物だが、40年後にはじめて読んでも価値の高さをかなり感じさせるものだった。話を直に聞ける機会がない伝説中の中世史研究者の二人の口から発言を聞くような至福な体験だった。ただ、多く指摘されたように読んでたくさん学んだというより、80年代における大事な問題提起を知るようになった感じ。個人的に市や贈与の前半と最後の日本史学史的な部分が最も興味深く読んだ。今でも議論する価値がかなり高い、日本史学史における「社会史」の潮流とそれへの批判をさらに知りたく思った。2024/08/10
-

- 電子書籍
- ビブリア古書堂の事件手帖III ~扉子…